|
|
|
|
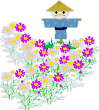 田植えも終り満々と水をたたえた稲田の上を涼風が通りぬける。瑞穂の国の原風景が今、目の前に広がっているが、よくみてみると昔と大きく様変わりしていることがわかる。昔なら今頃は蛙の大合唱で喧しいほどだったが、今はその声は聞こえない。また燕がきて子育てをする光景がどこでも見られたものだが、今はその姿も見えない。田舎の道を歩いていると、農薬による田園の破壊が確実に進んでいることが肌身に感じられる。 田植えも終り満々と水をたたえた稲田の上を涼風が通りぬける。瑞穂の国の原風景が今、目の前に広がっているが、よくみてみると昔と大きく様変わりしていることがわかる。昔なら今頃は蛙の大合唱で喧しいほどだったが、今はその声は聞こえない。また燕がきて子育てをする光景がどこでも見られたものだが、今はその姿も見えない。田舎の道を歩いていると、農薬による田園の破壊が確実に進んでいることが肌身に感じられる。我々は科学的合理主義はよいものだと信じて、邪魔者を殺しつづけてきた。だが、それが危険な思想だったということに、今ようやく気づきはじめている。 かつてWHO(世界保健機関)は、アフリカのマラリヤ患者の多い地域で徹底的なマラリヤ撲滅作戦を展開した。その結果、乳幼児に死亡率が十分の一に下がった。しかし十年ばかり後、その地域の住民のほとんどが餓死してしまった。マラリヤ患者がいなくなって、爆発的に人口が増加したためである。WHOは、はたしていいことをしたのか、悪いことをしたのか頭をかかえこんだという。 邪魔者は殺せという考えが進んだとき、我々は思わぬかたちで大自然の復讐を受けるわけだ。小さな智恵では、大宇宙の摂理はわかならいのである。 もちろん現代に生きる我々は、稲の虫を殺し、マラリヤを誘発する蚊を殺さなければならぬ。だが、そのとき、「すまぬ」という思いを忘れないで殺すべきだ。 「次の世はよき虫に生れこよと 手合せつつポリドールまく」 |
世界遺産・白神山地に連なる静かな町で児童二人が行方不明となり、死体で発見された。他殺の疑いが濃厚だが、まだ犯人は挙がっていない。最近、児童が誘拐されて殺されるという、いたたましい事件が続発している。  中国明代の洪自誠の「菜根譚」は儒仏道の三教兼修の立場から述べられた人生哲理の書で、永遠のロングセラーともいわれているが、その中に、「人は必ずしも誠実な人ばかりではないが、自分が人を信ずれば、少なくとも自分一人だけは誠実であったわけだ。人は偽り欺くような人ばかりではないが、自分が人を疑えば、少なくとも自分が人を欺いたことになる」という一節がある。 中国明代の洪自誠の「菜根譚」は儒仏道の三教兼修の立場から述べられた人生哲理の書で、永遠のロングセラーともいわれているが、その中に、「人は必ずしも誠実な人ばかりではないが、自分が人を信ずれば、少なくとも自分一人だけは誠実であったわけだ。人は偽り欺くような人ばかりではないが、自分が人を疑えば、少なくとも自分が人を欺いたことになる」という一節がある。かつての伝統社会では「菜根譚」が言っているように、人をだますより、だまされた方がいいと誰もが考えていた。親は子に、「だますよりだまされよ」と教えてきたのである。ところが最近では、「人を見たら疑え」と教えざるを得なくなっている。子供の教育が人間不信から出発しなければならないほど不幸な時代があるだろうか。 仏教では物が豊かになるにつれて心が濁ってくるのを劫濁(こうじょく)といっている。時代の汚濁である。だが、その汚濁の人にも「一切衆生 悉有仏性」といって、仏性という気高い素質が一様に備わっていると教えている。子供を殺して闇に潜んでいる殺人犯にも備わっているのだ。だが、その仏性の種ものが、固い石の上に置かれた種もののように眠ったままの状態になっているのが、今日の問題である。 |
 新緑の季節となってピカピカのランドセルを背負った一年生が喜々として通学している。中にはずいぶん高価なものもあるようだが、しかし、それがどんなに高価でも、ランドセルそのものは単なる物質。本当に値打があるのは、それを吾子に買ってやりたいと思った目に見えない親心である。 新緑の季節となってピカピカのランドセルを背負った一年生が喜々として通学している。中にはずいぶん高価なものもあるようだが、しかし、それがどんなに高価でも、ランドセルそのものは単なる物質。本当に値打があるのは、それを吾子に買ってやりたいと思った目に見えない親心である。昔、比叡山に正算という名僧がいたが、その母は郷里で吾子の身を案じ、あるとき見舞いのために使いをやらせた。使いの者は、「元気にしているだろうか。体に気をつけておくれ」と書かれた母の手紙にそえて、白米一袋を持参してきた。正算は大いに喜こび、早速、米をとり出して炊き、使いの者に一緒に食べようと差しだした。だが、使いの者は、それを見てただポロポロと涙を流すばかりで食べようとしない。そこで正算が、その理由を聞くと、使いの者は、 「このお米は母御が毎日あなたの身を案じたすえ、ご自分の黒髪を切って、それであがなったものです。だからこのお米の一粒一粒は、母御の黒髪一筋一筋に当たるわけです。それを思うと、とても・・・・」と答えた。 正算は言葉にならないほどの感動をうけた。それからは、いつまでも母にことを忘れまいとして残りの米粒を毎日の雑穀に一粒だけ混ぜて食べたという。 現代は物が栄えて心が滅ぶ時代といわれているが、その物が産みだされた背後の力をよく知ることができたら、心は決して滅ぶことはない。 5月15日は「母の日」。お母さん、ありがとう。 |
親の心配をよそに、結婚したがらない若者が増えている。「なぜ結婚しないの」と聞くと、「自由がなくなるから」という返事が多い。要するに、結婚したら人生の楽しみが減るから、というのである。 少子化が日本の行手に暗い影を投げかけており、要路者はその対策に苦慮しているが、「人生は楽しむためにある」という考えがなんとかならないかぎり、真の解決はむつかしい。少子化問題の核心は「哲学」の問題なのである。 結婚式に招かれていた来賓の一人の祝辞が思い出される。 「結婚おめでとう。ご両親は今日の日を、どんなに待ちかねていたことか。結婚はよいものだから、人間はやはり結婚しなければいかん。どうして良いかというと、自分の思いどおりにならない人が、いつもそばにいてくれて、それで自分が人間になっていくからだ」  と、その人は言った。身に覚えのある人には思わずクスクス笑いたくなるような祝辞だったが、しかし結婚というものの奥義をついたものだった。 と、その人は言った。身に覚えのある人には思わずクスクス笑いたくなるような祝辞だったが、しかし結婚というものの奥義をついたものだった。人生を自由気ままに生きた人は、つまらない。結婚して、こんなはずではなかったという思いをくり返すうちに、人は少しづつ一人前になっていくのだ。 「この泥があればこそ咲け蓮の花」 夫があり妻があり親があり、人生は思いどおりにならないという泥がなければ、深い楽しみという美しい蓮の花は咲かない。 |