|
|
|
|
 わが町「東国東郡武蔵町」も今月いっぱいでお別れ、4月1日からは「国東市武蔵町」になる。町村合併はどこでも名前でもめるが、ここも例外ではなかったようだ。しかし、伝統を生かした良い名前に落ち着いて、喜んでいる人が多い。どこやらで「南アルプス市」となったところがあるが、市民の間で今になって「しまった」という声が挙がっていると聞く。 わが町「東国東郡武蔵町」も今月いっぱいでお別れ、4月1日からは「国東市武蔵町」になる。町村合併はどこでも名前でもめるが、ここも例外ではなかったようだ。しかし、伝統を生かした良い名前に落ち着いて、喜んでいる人が多い。どこやらで「南アルプス市」となったところがあるが、市民の間で今になって「しまった」という声が挙がっていると聞く。皇室典範改正の問題は紀子さまのご懐妊で一時休眠となった。それまで「天照大神も女だった。女系天皇で何が悪い」という声が高かった。それが女性天皇と女系天皇の相違がはっきりしてくるのに伴い慎重論が高まり、それがご懐妊にニュースで決定的になった。 鰻は南方のどこかの深海で生まれ、苦労して故郷の川に帰ってくる。生きとし生けるものには、みな元でたところ、命の根元に帰りたいという本能が備わっている。 「ふるさとや臍の緒になく年の暮」(芭蕉)で、これは人間も例外ではない。当初、あれほど高かった改正賛成の声が、急にトーンダウンして慎重論に変わったのも、この回帰本能が目覚めたからではなかろうか。 人間は過去を背負い、未来をはらんで生きている。伝統だけに固執すれば停滞だが、それを無視した創造は根なし草だ。そこを孔子は温故知新(古きをたずねて新しきを知る)と両極端に奔ることを戒めた。 「根をしめて 風のまにまに柳かな」 |
高校生の娘をもつ母親から「娘が小遣いが欲しいからアルバイトをするという。そのアルバイトが「援助交際」なんです。父親がブン殴るというのですが、そんなことをしたら娘は家出するだけ。どう言って説得したらいいのか・・」と子育ての悩みを聞かされた。口論のいきがかり上に出た言葉だったようだが、「誰にも迷惑をかけずに自分の体でお金を稼いで何が悪いの。父さんだって汗水たらして自分の体で稼いでいるではないか」というのが娘さんの言い分だという。 戦後の躾教育は「他人に迷惑をかけるな」「自分のことは自分で責任をもて」で、それ自体は立派なことだが、こうした問題については無力である。  かつて「人を殺してなぜ悪いの」と問う子に、返答に窮した親のことが話題になったことがあるが、売春も殺人も論理で答えうる問題ではあるまい。「悪いことは悪い」と問答無用の次元でしか答えられない問題ではなかろうか。頭で考えて納得できないものは駄目だというのが今日の時代の流れだが、論理は万能ではない。野に咲くスミレは美しいというのは論理では説明できない。モーツアルトは美しいというのも同様である。嘘はいけないというのも同様である。 かつて「人を殺してなぜ悪いの」と問う子に、返答に窮した親のことが話題になったことがあるが、売春も殺人も論理で答えうる問題ではあるまい。「悪いことは悪い」と問答無用の次元でしか答えられない問題ではなかろうか。頭で考えて納得できないものは駄目だというのが今日の時代の流れだが、論理は万能ではない。野に咲くスミレは美しいというのは論理では説明できない。モーツアルトは美しいというのも同様である。嘘はいけないというのも同様である。論理で説明できない部分をしっかり教えるというのが、かつての日本人の伝統的な教育のあり方であり、それが外国人も驚くような国民の高い道徳性の源泉であったのだが、そのような意味で問答無用の教育のもつ価値を再発見していかねばならぬ時ではなかろうか。売春が無感覚になるゆな時代がごめんだ。 |
「いじめ」にあって不登校になっている中学1年の男の子から、 「和尚さん、なぜ僕は生きなければならないのですか」 と聞かれて宮台真司氏(都立大教授)のことを思い出した。氏は若者にカリスマ的人気のある人だが、この人が人生問題に悩む若者から「なぜ生きるのか」と聞かれて、「生きることに意味もクソもない。生きなければならない理由なんて、なにもないよ」と答えたら、その学生は自殺してしまった。そのことを思い出したので言葉を慎重に選びながら、だいたい次のように答えた。 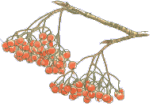 「それはむつかしい問題で、まだこれといった解答はないんだよ。だが和尚さんは、いろんなことを体験することで未熟な自分が一人前の人間になるために今ここに生きていると思っている。だから和尚さんの目からすれば、君が受けている今のいじめも、将来、君が大きく成長するために肥料なんだ。だから無駄ではないんだよ。これが将来、大きな花をさかせてくれると思って頑張ってくれ」 「それはむつかしい問題で、まだこれといった解答はないんだよ。だが和尚さんは、いろんなことを体験することで未熟な自分が一人前の人間になるために今ここに生きていると思っている。だから和尚さんの目からすれば、君が受けている今のいじめも、将来、君が大きく成長するために肥料なんだ。だから無駄ではないんだよ。これが将来、大きな花をさかせてくれると思って頑張ってくれ」こんな返事が暗く沈んだ少年の心に届いたかどうかわからないが、考えさせられる質問だった。カミユは、人間の奥底には、生きる意味を死にもの狂いで知りたがる願望が渦巻いているといっている。みな多忙のためにその音に気づかないが、かつて見ず知らずの婦人の家に上がりこんで彼女を惨殺して「人を殺す経験をしたかった」と言った高校生、友人の首を切断して「僕の存在は透明だ」と言ったA少年、みな渦巻く音に耐えかねての所業だったのではなかろうか。 |
定期検診で不整脈があるといわれ検査をうけた。結果は「要注意だが、まだ薬は不要」といわれヤレヤレだったが、その時、医師から「あなたの脈搏は1分間に80ある時もあるし、120ある時もある。不安定のようだが、これが正常なのです。たまにそれがいつもきちんと一定している人がいるが、これは異常で、かえって危ないのです」と医学常識を教えてもらい考えさせられた。 人生は悲喜苦楽で、人はみな悲苦を厭い、喜楽がいつまでも続くように願っている。だが、現実にはそうならないのが有難いので、もし、どちらか一方に一定してしまったら人はおかしくなる。西諺に「自然は最良の教師」とあるが、そうした法則を自然がこんな形で教えてくれているような気がして感じ入った。 あるお寺さんの奥さんに「仏さまの言葉」という詩がある。
|
「もったいない」は日本の古い言葉だが、これが今「国際語」に昇格しつつある。先鞭をつけたのは日本青年会議所だが、先年、アフリカ人女性初のノーベル平和賞受賞者となったケニアのマータイさんが、これを地球再生のキャッチフレーズに使いはじめてから輪が広がった。「汝、殺すなかれ」という仏の不殺生戒の教えがそのルーツではないかと思われるが、思えば物質文明の奔流の中で物をないがしろにしつづけているうちに、人類は環境破壊という難問に直面した。 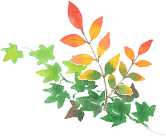 終戦の時、私は小学校2年だったが、あの頃はよく停電していた。暗闇の中で本を読みたいとせがむ私に、祖母がちびたローソクに点灯してくれながら、なにげなく言った言葉が思いだされる。 終戦の時、私は小学校2年だったが、あの頃はよく停電していた。暗闇の中で本を読みたいとせがむ私に、祖母がちびたローソクに点灯してくれながら、なにげなく言った言葉が思いだされる。「ローソクさまは有難いな。自分の頭に火をつけて、熱いあついといいながら光を出してくれている。もったいない」 思えば我々がいま忘れているのは、この物の見方ではないかという気がする。 それはどんな役に立つか、値段はいくらするかといった価値の立場で物をみれば、ちびたローソクなど無に等しい。だが、ひとつの命を分けあって産みだされたお互いという見方をすれば、物も自分のいのちの表れに外ならない。そんな立場から物を見ることができれば、それは意味の立場から物を見たことになる。 「もったいない」は「物体無い」の意で、物のもついのちを無視することだが、物心は一如だから物を無視していると人間の命まで無視されるようになる。 |