|
|
|
|
 「旅のお方、先日あなたのような人を泊めたら、その人が夜中に強盗になって皆が迷惑したのです。それから村の話合いで旅人は泊めないようにしました。そこにむしろがあるから、軒下でよかったら休んでもいいです。」 「旅のお方、先日あなたのような人を泊めたら、その人が夜中に強盗になって皆が迷惑したのです。それから村の話合いで旅人は泊めないようにしました。そこにむしろがあるから、軒下でよかったら休んでもいいです。」尼は仕方なくむしろを借りて横になったが、寒気と空腹で眠れない。そうするうちに月が出て見事な夜桜が浮かびあがった。それを見て尼に歌が生れた。 「宿かさぬ人のつらさを情にて おぼろ月夜の花の下臥せ」 今まで人の薄情さを恨んでいたが、しかし、家の中に休ませてもらっていたらこの見事な夜桜には出会えてないだろう。すると、あの人々の薄情さは、むしろ情ごころだったのかと気づいてこの歌が生れたわけです。 仏教では、ものごとが好都合に運ぶことを順縁といい、その反対を逆縁といっている。その逆縁の中に慈悲が感じられるようになったら、仏教では「智慧の目が開いた」という。開彼智慧眼は容易なことではないが、焦らずに努めたい。 |
 先日、ボケたお婆さんと、ひと時を過す機会があった。こちらが話しかけると脈絡のない返事が返ってくる。そうかと思うと急に「お母さん」という言葉がでてくることもある。教育者として人格見識ともに優れた方だっただけに、痛ましく思えた。だが、そう思いながらも、自分の気持ちが不思議に和んで、思わず笑顔がこぼれている自分に気づいた。人は誰かと向きあっていると、知らず知らずに自分の体面を考えたりして、心のどこかが緊張している。痴呆の人と話していて心が和むのは、その緊張感が解きほぐされるからだろう。そういえば、誰かが痴呆症のことを「ほとけ症」と呼んでいた。相手の緊張感を解きほぐし、癒してくれるからである。 先日、ボケたお婆さんと、ひと時を過す機会があった。こちらが話しかけると脈絡のない返事が返ってくる。そうかと思うと急に「お母さん」という言葉がでてくることもある。教育者として人格見識ともに優れた方だっただけに、痛ましく思えた。だが、そう思いながらも、自分の気持ちが不思議に和んで、思わず笑顔がこぼれている自分に気づいた。人は誰かと向きあっていると、知らず知らずに自分の体面を考えたりして、心のどこかが緊張している。痴呆の人と話していて心が和むのは、その緊張感が解きほぐされるからだろう。そういえば、誰かが痴呆症のことを「ほとけ症」と呼んでいた。相手の緊張感を解きほぐし、癒してくれるからである。お彼岸は悟りの世界にいこうと思いたつ日であるが、その悟りの世界にいく方法のひとつに布施という修行がある。その布施行の一つに無畏施という布施行があるが、これは相手に安心感を与えるもので、モノにはかえられない尊い修行とされている。赤子が安心して母にだかれて眠っているのは、無畏施という布施を母からもらっているからに外ならない。 自分はボケても、人に無畏施を施し、なお、人を癒す力が残されているということは素晴らしいことではなかろうか。 |
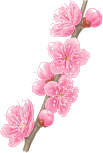 一度やるのに六時間かかり、それを三日に一度しなければならない。しかも器械の悲しさで融通がきかないから、決められた量以外は許されない。腹が減ったらおやつを食べる、喉が渇いたら水を飲むというような自由はない。愕然として返す言葉を失っていると、彼女が言った。 一度やるのに六時間かかり、それを三日に一度しなければならない。しかも器械の悲しさで融通がきかないから、決められた量以外は許されない。腹が減ったらおやつを食べる、喉が渇いたら水を飲むというような自由はない。愕然として返す言葉を失っていると、彼女が言った。「私はいつぞや、戦争で両手両足を失った人が、自分は最初から手足のないままこの世に誕生したのだと書物に書いてあるのを読んで、私もその人にならって、自分も腎臓のないままこの世に生れてきたのだと思うことに決めました。そう思ったら、すべてがまっさらです。こうして講師さんのお世話をさせてもらえることが、どんなに有難いことか。五体満足だったら、とてもこんな気にはならないでしょう。」 明日をも知れぬ命を生きている人の言葉は強い。 かつて、白陰禅師が「南無地獄大菩薩」と大書している字をみて感銘をうけたことがあるが、彼女の上に病気大菩薩を拝んだ気がして、思わず心の中で合掌した。 |
 今ここにいない人を、あたかもいるもののように思っている心境は、神に近いものがある。四国のお遍路さんの菅笠には同行二人と書かれている。これは一人で旅をしていても、常に仏さまと二人づれの旅であるという気持ちを表すものだが、宗教感情の極意は、すべてこの一点に納まっていく。 今ここにいない人を、あたかもいるもののように思っている心境は、神に近いものがある。四国のお遍路さんの菅笠には同行二人と書かれている。これは一人で旅をしていても、常に仏さまと二人づれの旅であるという気持ちを表すものだが、宗教感情の極意は、すべてこの一点に納まっていく。「この家は弥陀仏さまのお家じゃと思うてわが身を深くつつしむ」 これは筑紫の聖女と慕われた荒巻くめ女の歌だが、彼女は天涯孤独の一人住いの身ながら、常に仏と同行二人に日暮しであったことがこれでわかる。 東大総長であった南原繁氏は、「私が子供のころ、母に手を引かれて遠い親戚へ、つらい家庭の問題で相談に出向いた。その時、私が『お母さん、お月さまが一緒に歩いている』と言ったら、母が『そうだね、天には見る目、聞く耳があって知ってくださっているんだよ』と答えてくれて、その言葉で私の思いつめた暗い気持ちが開けた」と随想の中で述べておられる。 同行二人という素朴な感情こそ、自分が支えられ導かれる力の源泉である。 |
 松山のある裕福な家の老母は、リューマチを18年も病んでいた。ある人が見舞に行って、「お気の毒に」と言うと、彼女が答えた。 松山のある裕福な家の老母は、リューマチを18年も病んでいた。ある人が見舞に行って、「お気の毒に」と言うと、彼女が答えた。「ありがとう。これは本当につらい病気です。声がもれると皆を心配させるので歯をくいしばって我慢しようとするのですが、痛みがひどいと、つい呻き声が出てしまいます。でも私は泣きながら喜こんでいるのですよ。私は金持ちの家に生れて苦労を知らないまま、この家に嫁いできました。すると、この家がまた屈託のない家でした。この病気さえなければ、陽の当るところしか知らず、のんきな一生で終わっていたはずです。病気のために、夫や子供には迷惑ばかりかけていますが、自分はこれで一人前になって死ねると思ったら、泣きながら喜こんでいるのです。如来さまは、決して全部をとりあげはしませんよ。必ず何かを残してくれていますよ」 孔子が生活に困っていた時、弟子の子路がきて「先生のような立派な君子でも、お困りになる時はあるのですか」と聞くと、孔子が、 「君子もとより窮する。されど君子は窮すれども乱せず。小人は窮すれば即ち乱ず」と答えている。「乱ず」とは、とり乱すことだが、妙好人の言行は、窮してもいないのに乱ずることの多い吾身を照しだしてくれる。 |