|
|
|
|
 「あなた方の努力のおかげで、日本人が永らく忘れていた大切なものを、今少しづつ思いだしています」と礼を言うと、「いえ、私たちはそんなつもりで運動をやっているのではありません」と夫人の返事。「それはその通りでしょうが、結果として自然に日本の目覚めになっています。ご自愛して頑張って下さい。娘さんに再会できるように心から祈ります」といって別れた。 拉致されて20年にもなる娘を、まだ捜しつづける親。 思えば偉大な親の愛である。ある人が「臨終に近い母に添寝をしていると、夜中に母の手が伸びてきて私がふみ脱いでいる布団を着せてくれようとしている。急に涙があふれて、わざと寝たふりをしていた」と語っていたことを思い出す。 寺の過去帳に「尋源培根」と書かれたものがある。源を尋ねて根を培うと読むが、自分の命の源を尋ねる人は、期せずして神仏にめぐりあい、その出会いがその人の命の根を深く張らせるようになる。親が子を愛するのは犬猫も同じだが、命の出所を尋ねて生を深めることのできるのは人間だけだ。 |
若者に人気のある東京都立大助教授・宮台真司氏が、「何のために生きているのか」という人生相談をうけ、「生きることに意味もクソもない。まして生きなきゃならない理由なんてなにもない」と答えたら、彼の信奉者の青年が二人自殺した。後で氏は自著で、「自分の答えが結果的に彼の無意味感を高める方向に機能してしまったかもしれない」と述べている。  人間の心の奥底には、生きる意味を必死で知りたがる願望が渦巻いているが、この青年はその願望が満たされないのに耐えきれなかったのかも知れない。 人間の心の奥底には、生きる意味を必死で知りたがる願望が渦巻いているが、この青年はその願望が満たされないのに耐えきれなかったのかも知れない。アインシュタインは、「人は何のために生きているのかという問いに答えるのが宗教の役目だ」と言っているが、これに答えるのは容易ではない。だが、宮台氏と同じ質問をうけたら、何と答えたらいいのだろうか。 豊かな暮しをするため、子供を育てるためというのは、生きている目標であって目的ではない。目標は、それが満たされたら消えるものだが、目的は終生消えないものでなくてはならない。仏教ではこの人生を「日々道場」というが、この道場で経験しなければわからぬことを経験することで、人生を深めるために生きていると自分は思いたいが、どうだろうか。 |
これは詩人・坂村真民氏のもの。 戦前、朝鮮にいた氏は敗戦で命からがら妻子と港に辿りつく。そこへ日本から迎えの船がきたが小さくて全員は乗れない。そこで子女を先に乗せ、男たちは後に残ることになった。戦渦で祖国は荒廃し、後の船がくるあてもない。すると、これが生き別れになるかもしれぬ。これはそんな涙の中で生れたもの。 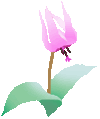 教育基本法改正の素案がまとまった。その骨子は「日本国の伝統の尊重」という条項を付け加えることにあるらしい。これは戦後、これを定める時、アメリカ側から拒否されていたもの。そして代りに与えられたのが「個性の尊重」「自主的精神」等々である。今、流行のジェンダーフリー運動は、これらの一種。これは男女の性差を無くそうとするもので、「男らしさ」「女らしさ」等は性差を助長するといって忌み嫌う。だが、それは本当に有害無益なものだろうか。 教育基本法改正の素案がまとまった。その骨子は「日本国の伝統の尊重」という条項を付け加えることにあるらしい。これは戦後、これを定める時、アメリカ側から拒否されていたもの。そして代りに与えられたのが「個性の尊重」「自主的精神」等々である。今、流行のジェンダーフリー運動は、これらの一種。これは男女の性差を無くそうとするもので、「男らしさ」「女らしさ」等は性差を助長するといって忌み嫌う。だが、それは本当に有害無益なものだろうか。詩人が子女を先に乗せ自分が後に残ったのは、自分が「男」であるという自覚がそうさせたのではなかろうか。 性差の自覚は時として人間性を高める。それは一種の精神的文化遺産として再考の余地があるのではなかろうか。男であるというだけで女より優れたもののように思うのは悪差別、性差を否定するのは悪平等で、共に避けて通りたいもの。 健全な個性は堅実な伝統の中でしか育たない。 |
上は歳末忙々の汽車旅行の中で読んだ本の一節。著者のフジ子さんは日本人の父と、スェーデン人の母の間に生まれ、5歳で母にピアノを習いはじめ、その後、ウィーンでデビューが決まった直後に風邪で聴力を失った。食べるためには働かなくてはならない。耳を治療しつつピアノ教師になり、みごと再起をはたした人である。 この一節に出あって、以前、人に教えてもらったことが思い出された。「辛」という字は「からい」とも「つらい」とも読む。その辛に「一」を加えたら「幸」になると彼は言った。なるほどこれが文字の妙味か。幸せというと甘いもののように思うが、実はつらさの中から味わいとっていくものだということが、これでわかる。 新年をむかえたが、世の雲行きは内外ともに。あまり甘くない。こんな時こそ活眼を開いて「辛」に「一」を加えていきたいものです。 皆様のご多幸をお祈りいたします。 |
これは亡父の葬儀で、会葬者への謝辞の中で喪主が述べた言葉の一節。久方ぶりによい言葉を聞いたと思いだった。 戦後、「個」が強調されるあまり、「公」のもつ意義が軽視されがちである。親子関係でも、親は親、子は子という弊害が目立ちすぎる。 何年か前、鹿児島の知覧市で、いじめにあった中学生が首吊り自殺をした。すると何日かして、今度は、いじめた方の父親が「申し訳ない」と遺書を残して農薬自殺をした。そのことで、テレビのワイドショーに出ていた某著名人が、「親と子は別なのだから、そこまでする必要はなかった」という意味の発言をしていた。 自殺をすすめるわけではないが、実際に自殺した人が出た以上、その責任感の強さと、親子の絆の深さに、まず頭を下げればよいのに、と思ったことがある。 法然上人は九才の時、武士であった父が暗殺された。死の間際、父は子を呼んで「お前が敵討ちをすれば争いは永久に絶えないことになる。だからお前は、このことは忘れて、これから生きていきなさい」と遺言して息絶えた。「父の遺言忘れがたく」と上人は晩年に至るまでよく言っておられたという。 養うだけが親でない。子を導く責任感をもった人こそ、真の親だろう。 |
経験がないのでお断りしょうかと思ったが、結局、「私でよかったら参りましょう」といって出かけた。 読経しながら思ったことは、仏典に「一切衆生悉有仏性」という言葉があるように、我々の祖先は全てのものに命があると思っていたということである。魚や牛馬の中にも、山や海や森の中にも、井戸や池の中にも命があると考えて、自然の中から生まれてきたのが人間だから、自然と仲よくすることが自分が幸せになる道だと考えてきたのが、我々の祖先である。 ところが、西洋の考え方が流れ込んできて、それはアニミズムだ、おくれた後進国の宗教だと言って蔑すむようになった。西洋の考え方では、自然は人間の力で征服するためにある、魚や牛馬は人間の幸せに奉仕するために存在しているとなる。これを人間中心主義という。 その人間中心主義が今、いたるところで破綻しかけている。その代表が環境問題だろう。海も山も痩せ細ってしまいつつある。二十一世紀の可能性を示すものは、全てに生命ありとする穏やかな東洋の考え方ではなかろうか。 |