|
|
|
|
年末になると私の寺では仏名会という法要が営なまれます。一年の間に積み重ねてきた罪を懺悔する法要ですが、その罪のことで三浦綾子さんの小説の中に、こんな話があったのを思い出します。 ある青年が牧師さんのところへ来て、「あなたは我々にいつも懺悔せよと言いますが、これがどうしてもわかりません」と言います。すると牧師さんが、「では大中小の大きさの違う石を三個持ってきなさい」と言います。青年が言われたとうりにすると今度は、「それをもとあった所に戻してきなさい」。青年は大中の二つは地面に跡が残っていたから戻せたが、小指の先ほどの小さな石は痕跡がないので戻せない。すると牧師さんが言った。 「人殺しや泥棒したことは記憶に残るから懺悔できるが、小さな罪はわすれているから、まだ懺悔してないんだよ」 その小さな罪ということで、ある小学生の「運動場」という詩が思いだされる。
|
今年の秋は、うち続く大型台風で弱りはてているところに中越地震で、日本列島は、かつてあまり記憶にない受難の中にある。毎日報道されている災害ニュースをみていて思いだされたのは良寛和尚のこと。新潟県出雲崎に住んでいた良寛さんは今度のような大地震に遇い、その時、当地随一の富豪であった酒造家の親友が、一夜にして全財産を失ってしまった。良寛さんが、その友人宛に出した見舞状が残されているが、その手紙は、  「地震はまことに大変にて候。野僧草庵は何ごともなく、親類中死人もなく、めでたい候」という書き出しで、次にあなたのようないい人が、こんなひどいめに遇って泣かねばならぬ姿を見らねばならないのも、私が長生きしたからです。長生きもわびしいことです、と続き、最後に 「地震はまことに大変にて候。野僧草庵は何ごともなく、親類中死人もなく、めでたい候」という書き出しで、次にあなたのようないい人が、こんなひどいめに遇って泣かねばならぬ姿を見らねばならないのも、私が長生きしたからです。長生きもわびしいことです、と続き、最後に「しかし、災難にあう時は、あうがよく候。死ぬる時には死ぬるがよく候。これはこれ災難をまぬがるる妙法(一番よい方法)にて候。」 という文章で終わっている。 問題は最後の一節だが、災難に泣く人に、一見非情な言葉に思える。だが、何度も口ずさむうちに不思議な安らぎを覚えるのは私一人だけだろうか。 世間的な常識を超えた仏智の中から湧き出る言葉には、尽きせぬ味わいがある。 歌人の吉野秀夫氏は病で倒れた時、この言葉に倣って、 「われもまた聖に口をあわせていう 死ぬる時は死ぬるがよく候」と詠んでいる。 |
台風の爪跡深い山野に、今年も彼岸花が萌えだした。 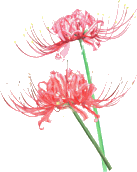 先般、宇佐市の豊前善光寺で恒例の三泊四日の念仏と法話の会が催されたので参加した。ここ3年ばかり、毎年顔を見る三十代半ばの青年が今年も来ていて、朝5時から夜9時までのスケジュールを、よく精進していた。今回はじめて挨拶をして雑談しているうちに、彼は弁護士になるため都会で勉強中に膠原病に冒され、故郷の北九州で療養中であること、そして病状の回復は困難で初心は断念せざるを得ない身の上であることを聞かせてもらった。その彼が、 先般、宇佐市の豊前善光寺で恒例の三泊四日の念仏と法話の会が催されたので参加した。ここ3年ばかり、毎年顔を見る三十代半ばの青年が今年も来ていて、朝5時から夜9時までのスケジュールを、よく精進していた。今回はじめて挨拶をして雑談しているうちに、彼は弁護士になるため都会で勉強中に膠原病に冒され、故郷の北九州で療養中であること、そして病状の回復は困難で初心は断念せざるを得ない身の上であることを聞かせてもらった。その彼が、「でも、このおかげで仏の教えに遇うことができました。あのまま元気だったら、私は一生手を合わせることを知らなかったでしょう」 と爽やかに語るのを聞いて、残暑の中に一陣の涼風に遇った心地だった。 彼岸とは向こうの岸という意味だが、それに対するものがこちらの岸で、これを此岸という。インドの竜樹菩薩の大智度論に「生死をもって此岸となし、涅槃をもって彼岸とす」とある。生死の岸とは利害損得、悲喜苦楽に捉われて身動きならぬ世界で、迷いの世界、現実の世界がこれである。涅槃とは、それから一歩でた世界で、さとりの世界、理想の世界。 生死の中に沈んでいた者に、新しい視点が開けて感謝の種が発見できたら、その人は涅槃の彼岸界に一歩足を踏み入れたことになる。 |
「三郎さん、爆弾を抱えていく時は南無阿弥陀仏と称えておくれ。これが母のたのみです。忘れないでくれたら、母はこの世に心配なことはひとつもない。忘れないで称えておくれ。今度会う時は阿弥陀さまの前で会いましょう。これ何よりの私のたのみです。忘れないでおくれ」 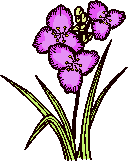 また息子から母への別れの手紙もあった。 また息子から母への別れの手紙もあった。「母上お元気ですか。永い間、本当に有難うございました。我六才の時より育ててくだされし母。継母とはいえ世の此の種の女にある如き不詳などは一度たりともなく、慈しみ育ててくださりし母、有難い母、尊い母。僕は幸福でした。遂に最後まで『お母さん』と呼ばざりし僕。幾度か思い切って呼ばんとしたが、なんと意志薄弱な俺だろう。母上お許し下さい。さぞ寂しかったでしょう。今こそ大声で呼ばせていただきます。お母さん、お母さん、お母さんと」 記念館の詣でると、今の我々が忘れているものに気づかされる。それは燃えるような家族愛であり、祖国愛であり、自己犠牲の心情等である。戦争の悲劇を歎くあまり、当時のことはすべて間違っていたと捉えられるむきが多いが、しかしそれは、戦没者たちが持ち得た崇高な精神を冒涜することになりはしないか。 |
経営の神様・松下幸之助氏のことが思いだされる。氏は、いろんな幸運のおかげで今日があると常々感謝していた。  第一の幸運は、貧しい多難な子供時代を経験したこと。氏は戦争で全財産を失ったうえ莫大な借金を背負いこんだ。あの苦境を切り抜けられたのは、少年の頃の体験があったから。第二の幸運は病弱であったこと。氏は事業を始めたばかりの一番大切な時に結核で倒れた。自分はベッドから離れられないので、全て人に頼まねばならない。その苦境の中で人を見る目が養なわれた。第三は自分に学歴がなかったこと。小学校中退の氏の周りにいる人は、みな自分より高学歴の人ばかり。それが自然に、「自分が話すよりも前に、まず人の話を聞いて何か学びとろう」という習慣を生んだ。今日の自分があるのは、こうした幸運のおかげだと氏は述懐しておられる。貧乏、病弱、無学は人の嫌うものだが、それを幸運と拝めるのは氏の心境が深められていたからだろう。 第一の幸運は、貧しい多難な子供時代を経験したこと。氏は戦争で全財産を失ったうえ莫大な借金を背負いこんだ。あの苦境を切り抜けられたのは、少年の頃の体験があったから。第二の幸運は病弱であったこと。氏は事業を始めたばかりの一番大切な時に結核で倒れた。自分はベッドから離れられないので、全て人に頼まねばならない。その苦境の中で人を見る目が養なわれた。第三は自分に学歴がなかったこと。小学校中退の氏の周りにいる人は、みな自分より高学歴の人ばかり。それが自然に、「自分が話すよりも前に、まず人の話を聞いて何か学びとろう」という習慣を生んだ。今日の自分があるのは、こうした幸運のおかげだと氏は述懐しておられる。貧乏、病弱、無学は人の嫌うものだが、それを幸運と拝めるのは氏の心境が深められていたからだろう。「思いは行いとなり、行いは習慣をうみ、習慣は品性をつくり、品性は運命を決定する」と故人の言葉にある。 よき思いができて、よき運命を開いていきたい。 |