|
|
|
|
浄土宗の寺々では12月になると一年最後の法要として仏名会を営むところがある。京都嵯峨野の清涼寺の三千仏名会は名高いが、そこでは三日間に三千の礼拝をして、一年に犯した過失や罪悪を懺悔する。 懺悔をすすねる僧のところに一人の青年が来て、「私は悪い事をしたら、その都度すみませんと謝っているので、もう懺悔は済んでいる」と言った。 すると僧は、「大、中、小の三種の石を拾ってきなさい」と言う。そこで青年は言われたとうりにすると、今度は「それをもとあった場所に戻してきなさい」。 大は今まであった所に跡がはっきりと残っていたので、すぐ戻すことができた。中もかすかに跡が残っていたので戻すことができた。だが小指の先ほどの小さい石は跡が全く残ってないので戻せない。「これは戻せません」というと、僧は「我々には罪を犯しても意識しなかったり、忘れてしまっていることが沢山ある。だから君はまだ懺悔が済んでないのだよ」と言った。 百円と百万円盗んだでは、世間的には大違いである。百円は微罪だからお小言ですむが、百万円は重罪だから、ただでは済まない。しかし、仏さまがごらんになると同じで、共に盗人である。殺人に対しても同様。実際に手で人を絞め殺したのと、心の中で殺してやりたいと思ったのは同じで、共に人殺しなのである。そのように考えると盗人、人殺しでない者はないから人はみな罪悪の凡夫という。 造りおく罪は山ほどあるなれば閻魔の帳につけどころなし(沢庵) |
倉庫の中で埃をかぶっていたこたつをとり出し、足を入れてホッとしていると「足なし禅師」のことが思いだされた。岐阜県大垣市にお住いであった小沢道雄師のことだが、師はシベリアに抑留されていた時、重傷を受けて労働不能となり日本に送還されるため列車で牡丹江へ向う途中、足が凍傷にかかり両足切断となり、義足になって僧侶になった人である。 日本に帰ってきたある日、こたつに入ろうとした師は義足をガチャガチャはずして行儀よくそろえているのを見た知人が、「便利にできていますね」と逝ってしまって、「しまった、心ないことを言った」とハッとしたとたん、「あんた達は不便だのう」とけろっとした師の言葉が返ってきたそうである。 師の著「本日ただ今誕生」によると、師が両足切断したのは27才の時で、以来、師を苦しめたものは有ったものが無くなったという喪失感だった。その苦しみを「安らかな心にならせたまえ」と観音さまに祈ったが、祈れば祈るほど苛立たしさがつのる自分に気づいて、祈って仏が助けてくれないなら、祈ることを止めようと決心した瞬間、暗い心の中に光がさしこんできた。 「自分の考え方が間違っていたのだ。27年間有った足が無くなった。この考え方が自分を苦しめていたのだ。そうではなくて両足ないまま、27才の時シベリアの荒野でオギャーと生まれてきたのだ」。 そのように方向転換した日から、師は極楽の人になったのである。 |
子殺し、親殺しのニュースを毎日のように聞くにつけ、僧に三人いるという話を思いだす。持戒僧、無戒僧、破戒僧の三人である。理想としたいのは持戒僧で、これは仏の戒めをよく守る人。良寛和尚は蚊も手で払うだけだったというが、我々は「血を分けた仲とも思えぬこの憎さ」でバチンだから、持戒僧にはなれない。 次の無戒僧とは、仏の戒めを教えてもらったことがない人である。かつて「人を殺してなぜ悪いのか」という若者がいて問題になったことがあるが、彼等は悪いと教えてもらえなかったのである。 僧の一番理想とすべきは破戒僧である。彼は極悪の代表のように言われているが、決してそうではない。彼等は意志が弱いから、いつも戒めを破っているが、しかし、「殺すな」という仏の戒めはよく知っているので、その都度「しまった」と思っている。たとえ仏の戒めを破っても破るものを持っていることが大事で、神仏の戒めは守るためにあるのではなく、破るためにあると知るべきである。 数学者の藤原正彦先生は子供のころ生傷の絶え間がない腕白だったが、そんな子に父はいつも「喧嘩しても相手が謝ったら許してやらねばいかん」と厳しく言いつけていたそうである。先生が、「なぜそうしなければいけないのか」と聞いても「卑怯だからいかんのだ」というだけでそれ以上の説明はなかった。 持戒僧には及びもつかぬが、無戒僧だけにはなりたくない。彼等は教育被害者というべきで、今日の人殺しの横行は教育被害者のなせる業としか思えない。 |
終末期医療の専門科・大津秀一医師の「死ぬとき後悔すること25」(至知出版)を詠んで考えさせられた。無量寿経に 「大命まさに終らんとするとき、悔懼交り至る」 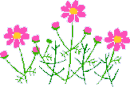 とあるが、人間最後が迫ってくると、悔懼、つまり後悔や恐怖が交々に襲ってくるものらしい。それをまとめたのがこの本だが、その中には、「タバコを止めなかった」、「結婚しなかった」、「遺産をどうするか決めなかった」といった次元のものから、「悪事に手を染めた」、「自分が一番と信じて疑わなかった」、「感情にふりまわされた一生を過した」、「神仏の教を知らなかった」など内面的なものを後悔しながら死んでいった人が何人もいたことを知って私は「人は死に向って衰弱していくのではなくて成熟していくのだ」と言った故人の言葉を思い出した。 とあるが、人間最後が迫ってくると、悔懼、つまり後悔や恐怖が交々に襲ってくるものらしい。それをまとめたのがこの本だが、その中には、「タバコを止めなかった」、「結婚しなかった」、「遺産をどうするか決めなかった」といった次元のものから、「悪事に手を染めた」、「自分が一番と信じて疑わなかった」、「感情にふりまわされた一生を過した」、「神仏の教を知らなかった」など内面的なものを後悔しながら死んでいった人が何人もいたことを知って私は「人は死に向って衰弱していくのではなくて成熟していくのだ」と言った故人の言葉を思い出した。悪事に手を染めたことを後悔するのは、心が清浄になっているから。他人を馬鹿にしてきた、身勝手な感情にふりまわされてきたことを後悔するのは、心が貧しければできない。「神仏の教を知らなかった」ことを後悔するのは、自分の無力を感じているからで、人は無力を感じるときもっとも神に近くなる。 微笑して礼を言って死ぬ人だけが仏に照らされているのではない。後悔の涙を流しながら死ぬ人もまた照らされているのだから、安心して死んでいけばいい。 |
叱られた恩を忘れず墓まいり 「恩」という字が「因」と「心」を組み合わせてできているのは、そのものを成り立たせている原因を心に刻みつけるという意味だと聞いたことがある。盆の迎火や送火を焚いての墓参は、自分の命のルーツを知って、それに感謝しようとする心のあらわれといってよいだろう。 仏教研究家だった田中忠雄先生が、旧制佐賀中学在学中に、ドイツ語の恩師岩本秀雅教授に向って、「恩を受けた人々に感謝し、天地自然の恩恵にまで感謝していたら、人間はその重さに圧しつぶされてしまう。そんな報恩感謝などという後向きの考え方は僕はわかりません」というと、岩本先生は悲痛な表情で「報恩感謝の心がわからぬというのでは、どんなに勉強しても、君の前途に不吉なものを感じる」といって黙ってしまわれた。それから田中先生はいろんな思想の遍歴をされて、その間、過激思想の持主として2年間刑務所の独房につながれた時、恩師の予言に気づいて慙愧の念から報恩感謝の気持の重大さに目覚められたとのことである。 経典に金持の家の愚かな兄弟が、ある日、毎日食べているお米は、どこからやってくるかという議論をしたという話がでてくる。兄が「倉の中から湧き出てくる」というと弟は「いや、臼の中から湧き出てくるのだ」といった。 原因を知らないということは無知ということなのだという話である。 |
久しく絶版となっていた山形道文著『われ判事の職にあり』が復刻(佐賀市福博印刷出版部門「出門堂」刊)された。戦後間もない食糧難の時代に闇米買いを拒んで餓死した一判事の記録だが、当時、新聞に報道された記事を読んで、亡母が涙を流していた遠い昔を思い出した。 食料難という時代があったことすら知らぬ世代が増えているが、当時は食料管理法というのがあって米は配給制だった。しかし量が少ないので、闇米を購入する者が後を絶たず、起訴される被告が相次いでいた。法に絢ずる決意をした判事は配給だけの生活を貫き、幼い二人の子に配給米のほとんどを与えたため栄養失調で倒れたのである。時は昭和22年、判事の名は山口良忠、享年33才の死だった。次は死の床でつづられたある日の日記。
|
「より強い家族がより強い国をつくる」といって年頭教書で、経済、軍事よりも家族の強化を政治の最高重要課題としたのはアメリカのクリントン元大統領。家族の絆の大切さを思う時、いつも思いだすのが毎月、山寺で例会がもたれている断酒会のある日の光景である。二十代から毎日一升の酒を飲みつづけて、家庭崩壊の寸前までいった経験のある人が、泣きながら体験報告をした。 「酒を飲むと職場も長つづきせず、いつも金に困っていました。そんな時、たまたま長男が新聞配達でためた金を発見しました。泣いて抗議する子を蹴飛ばして金をとりあげ、そのまま酒屋に走っていってヨレヨレになって帰宅しました。 その時、激しく泣く子に妻が言ったのです。『父ちゃんを怨んではいけないよ。本当はやさしい父ちゃんなんだよ。酒に狂っているだけだよ。かわいそうな父ちゃんなんだよ』。私は妻の言葉を聞いて、これで酒をやめられなかったら死のうと固く心に誓いました。そして断酒に成功して1年。私が断酒できたのは、一重に妻と子供のおかげ、家族のおかげです」。 政治家はマニフェストを掲げるが、家族の強化を謳う声は小さく、夫婦別姓といって家族の弱体化を狙う声は高い。かつて「英国病」という病気に冒され死の寸前だったイギリスを再生させたのはサッチャー首相だが、彼女は社会主義が崩壊させようとしていた伝統的な家族間を復活させることに力を注ぎ、それを為せば教育や社会の問題の多くが解決することを、まざまざと見せてくれた。 |
春は就職のシーズン。不況で思うような就職口の見つからなかった人もいるだろうが、その時、ジメジメと暗い心になるかどうかが人生の岐路になる。 これはある短大で先生をしている人の話。ある女子学生が「出版社で働きたい」と言うので「出版社はかなりの学力がいるよ」というと「お茶くみでもいい」という。そこである出版社に頼んで雑用係に採用してもらった。ところが3年ほどして彼女が菓子箱 「えらい出世だね」というと、彼女は話し始めた。お茶くみの彼女には有名人との交流があったりする同僚が羨ましくて仕方なかった。しかし羨んでも仕方がないと腹が決まり、それから来客においしいお茶を飲んでもらおうと故郷の母がやっていたことを思い出しながら研究を重ねた。そんな折、その出版社では新しい女性雑誌を創刊することになり、新しいスタッフを選ぶ会議があった。その折一人が「女性の雑誌は身近なことへの心くばりが重要だ」と言った。すると次の人が「最近来社する客が、ここの会社のお茶はおいしいといっている」と言った。するとお茶はあの雑用係がやっているのだということになって、そういう女性こそ女性雑誌の編集には必要なのだという意見が出て、思いもかけず自分が抜擢されたというのである。 釈尊は涅槃の時、「自らを闇夜の灯とせよ」と遺言した。これを自灯明といっているが、これは他を羨まず自分にふさわしい道を歩いていくことである。 |
高校の同級生が念願の四国八十八ケ所めぐりを終えたと報告にきてくれて、旅で拾った土産話を聞かせてくれた。 昔、松山に衛門三郎という長者がいて、豪勢な暮しをしていたが、ケチンボで皆に嫌われていた。ある日、一人の僧が托鉢にきた。断ると次の日も次の日も来る。カッときた三郎は僧の差し出す鉄鉢をとって地面に叩きつけた。鉄鉢は八ツに割れてとび散った。それから彼の八人の子が次々に変死をとげていった。「さてはわが所業の故であったか。僧に詫びをいいたい」と思い、どうしたら会えるかと古老にたずねた。すると「あの方なら八十八ケ所を順に巡礼しておいでになっているはずだから、追っていけば会える」と教えられ、すぐさま一番札所からまわりはじめた。だが二十数回まわっても会えず、そのうち三郎は疲れて病気になってしまった。「こうまでしてお会いできぬのは、自分の歩き方が間違っていたからにちがいない。今度は逆にまわってみよう」と思って振り返ったら、なんとあれほど捜していた僧が目の前に立っていたという。 これは伝説だが、この振り返るというのは味わい深い言葉だと思った。 さみしくなったらおヘソをみよう あなたがひとりじゃなかったこと 思いだせたらきっと大丈夫 これは昨年の新聞広告コンテストで最優秀作品に選ばれたコマーシャルの一部。 心が滅入る時は、親に抱かれて幸せを祈ってもらった過去のあったことを振り返ったら、そこから再生の力をもらうはずだ。 |
南極海で日本の捕鯨船団に対して過激な攻撃を続ける米国のシー・シェパード(SS)が、今度は地中海での日本のマグロ漁船に対しても同様の行動をとると宣言した。調査捕鯨より動物の生きる権利の方が重要だと考えている彼等には、鯨肉を食う日本人は鬼畜のようにみえるのだろう。しかし彼等には鯨肉を食う文化はないが、鯨から燃料や工業油などは採ってきた。江戸末期、ペリー率いる黒船が日本に来航した目的のひとつは、米国捕鯨船団に食糧と水の提供を求めるためだった。それが石油の掘削に成功して鯨油が不要になっただけである。 鬼畜日本を叫ぶSSの人をみていたら二十年前、山口県長門市にある鯨の墓に詣でた時のことを思いだした。あの付近は鯨が一頭捕れたら七浦潤ったといわれた地帯だが、捕った鯨の腹を裂くと胎児が出てくることがある。そんな子鯨をあわれんで建てられたのが鯨の墓である。表面には「業尽有情雖放不生、故宿人天同証仏果」という文字が彫られていた。現代語訳すれば「あわれな子鯨よ、お前は海に放してやりたいが、もう生きられないだろう。ならば念仏回向の功徳をいただいて、今度生まれかわってくる時は人間界に生れて、同じ悟りの道を歩む人になっておくれ」という意味となろう。墓の近くにある浄土宗向岸寺には、鯨の位牌と子鯨の過去帳があり、今も毎年、回向の法要が営まれている。 人間は生きる資格があるから他の動物を殺して生きているのではない。万物同根だから生命の価値は平等。だから他の動物に赦してもらって生きているだけ。 |
年末の大掃除をしてお寺も新年を迎えました。そのことで先日こんな話を聞いて考えさせられました。ある会社では社長以下全員が手分けして清掃して新年を迎える。そのとき以前は、きつい所は若手がやり、楽な所は上役がやるという区分けが自然にできていた。それが最近はむつかしくなったという。「上役は給料が多いのだからきつい所をやり、若手は少ないのだから楽な所をやる。それが平等というものではないか」と主張する者がでてきたからです。 親と子がオレ、オマエの対等関係となり、先生と生徒はトモダチ感覚がよいとなると、こんな考え違いがおこるようになる。 政治や社会が平等と公平を目指すのは当然だが、この人生は不平等だらけ、不公平だらけ。色の白い人もいれば黒い人もいる、頭のいい人もいればわるい人もいる、交通事故で死ぬ人もいれば、同じ車に乗っていて助かる人もいる。それなのに平等と公平が簡単に手に入ると思わせる甘い教育をして、それが実現しないのは政治や社会のせいだと教えるのは残酷なことではなかろうか。 三才のとき脱疽でダルマ娘となった中村久子さんが、口に針を含みお手玉を縫って友人に贈ると、唾がついて汚いと捨てられた。悔しさを母に訴えると母は「バカにされて悔しいのなら唾のつかないお手玉を縫いなさい」と言うだけだった。それから彼女は努力して唾一つつけずに、どんな縫物もできるようになった。 今必要なのは安易な平等教育ではなく不平等に耐えうる教育ではなかろうか。 |
師走です。便利な世の中になったのだからヒマになってよさそうなのに、最近はかえって年中師走のような感じ。忙しいことを生甲斐にしているような人がいますが、しかし忙しいという字は「りっしんべん」に「亡」と書く。「りっしんべん」は心だから、心が死亡するのが忙しいという字。だから忙しいという字は、あまりめでたい字ではない。 くちぐちに忙しとのみ明け暮れの心にひびくなにひとつなく これは吉野秀雄さんの歌。忙しいと外のことばかりが気にかかり、何ひとつ心にひびくものはなく生涯をむなしく終ってしまうことになりかねない。 その辣腕ぶりが世人から強盗とあだ名されたこともある大実業家の秘書が、その人の死後、思い出を語った一文の一節が思いだされます。 彼は死期が迫ると若い秘書の手をとり、「おまえの若さと、オレの全財産を交換しよう」と何度も泣きくどいた。そして最後は、「暗い、暗い、オレは間違っていた」とつぶやきながら息絶えたという。いたましい話です。 歩きながら考える 急いで通りすぎた人の 気づかなかった野の花がみえる  草が語りかけてくる 草が語りかけてくる私にふりそそぐ太陽の愛 走れなくてよかった 決して人の後を歩んでいるのではない 前へ前へ 我が歩みに心をこめて悔いなく 上は足に障害のある古林泰子さんという少女の詩。ぽつぽつしか歩けなかったから、彼女には急いで通りすぎた人には見えなかった野の花が見えたのです。 |
 大腸ガンの手術をうけることになった知人を見舞うと彼が言った。 大腸ガンの手術をうけることになった知人を見舞うと彼が言った。「みんなからがんばれ、がんばれと激励される。有難いのだが、しかしそれがなにか心の負担になってね」 入院経験のある自分には、彼の気持がよくわかるような気がした。心細い気持になっているのが病人。その病人にがんばれの激励は、時として病人の気を滅入らせる結果になることがある。 ものの言いかたはむつかしい。末期ガンの人は死の一週間ぐらい前から死を予感しているといったのは、ある看護婦さん。そんな時に病人が一番よろこぶのは、「私はもうダメです」といったとき、「そんなことはありませんよ」という言葉より(勿論それも必要なときがある)、「私もやがて死ぬのですから」という意味の言葉を、それとなくほのめかすことが一番のなぐさめになることが多いと彼女は言った。いわゆる“死の連帯感”を表すのである。 病気見舞のときは、「お大事に」などは一番無難な言葉だろうが、私の場合は「佛さまが一番あんたにふさわしい道を選んでくれるよ」と言ってくれたのがうれしかった。戦場医学の父といわれるフランスのパルに「我、繃帯し、神これを癒したもう」という言葉がある。生死は所詮、人間をこえた大いなるもののみ力によるのだから、病の時はその原点を思いだし、おまかせして、のんびりとやっていこうというような意味の言葉が一番ふさわしいのではないかという気がする。 |
膠原病を患う婦人を見舞ったら「こんな体になって役立たずの人間になってしまいました。早く死んだ方が世のためと思うが、若い者が変な死に方されると孫娘の縁談にさわると言うので、それもならず・・・」と老いと病の嘆き。 「役立たずの人間になったとあなたは言うが、何かやることが残されているから生かされているのじゃないですか。何もやることがなくなったら仏さまが引きとってくれますよ」と話して帰った。 向野幾代著「お母さん、ぼくが生れてごめんなさい」(扶桑社)には、山田康文君という脳性マヒの肢体不自由児の歌が紹介されている。
|