|
|
|
|
9月は敬老会のシーズンである。「高齢化社会」というと老人が増加して社会のひずみが大きくなるという暗い響きがあるから、お年寄が多くて芽出度いという感じのする「長寿社会」と呼んだらどうかという提案もある。先般、そういう長寿社会を生きる芽出度い老人の話を聞いて、思わず拍手した。 ある家でお年寄たちが話をしていたが、一人のお年寄が目が薄くなった、耳も遠くなった、足も弱くなったと言い出した。すると、それを聞いていたその家の孫が、「でもうちのママはそう言ってなかったよ」と言いだした。これを聞いたお年寄が「ママはどう言っていたの」と聞くと孫が、「いつもあんなことを言っているが口だけはいつまでも達者だと言っていたよ」と言った。 これでその場の空気は一瞬氷りついたようになったが、しかし老婆の一言でそれはすぐに明るい笑声に変ったという。 「せめて口だけでも達者だと言ってくれていたかい、うれしいね」 「百才まで生きていても、本当の教えに遇わなかったら、本当の教えに遇った人の一日生きるにも足りない」と法句経にあるが、本当の教えとはなんだろうか。 それが視点をかえてものを見るという教えで、そのようなものの見方ができるようになったら、「智慧の眼」が開けたという。智慧とは「転依の義」といわれているように、立場をかえてものをみることができる心の力で、それは静かな心になったとき、山野清水のように心の中ににじみ出てくるものである。 |
お盆が近づいた。お盆は別れた人がこの世に帰ってくる時であると教えられている。十三日がきてお墓にお参りして、家に帰って仏壇に手を合わせていると、目には見えないけれど亡き人が帰ってきたのだなという気にさせられる。 「帰る」という言葉には、なにか心ひかれるものがある。帰るとはもと出たところに戻るという意味だが、そうなって人ははじめて落ち着く。 ある婦人がこのように話すのを聞いたことがある。彼女が時たま故郷の家に帰るとお母さんが「お帰えり」といって迎えてくれていた。そのお母さんが亡くなって次に帰ってきた時のことである。今度は兄のお嫁さんが「いらっしゃい」といって迎えてくれた。その時、母が「お帰えり」といって迎えてくれていた言葉の意味の重大さにはじめて気づいて涙が出て仕方なかったというのである。 「帰れるから旅は楽しいのであり 旅のさみしさを楽しめるのも わが家にいつか戻れるからである」とは癌で逝った作家高見順さんが死の淵でよんだ詩の一節である。 法然上人は臨終の時、心配して見守る弟子に、「私はどこへ行くのでもない、これから私は私がもと出た所、仏さまの国に帰っていくだけなのだ」と言っている。帰る所があるということはもっとも癒されることであり、人間の一番の幸せである。 里がえりしてきた亡き人々に、やはり家族のもとに帰ってきてよかったと喜んでもらえるような楽しいお盆にしたいものです。 |
母の日は五月晴れだった。高村光太郎の「母をおもう」の一節に 「夜に目をさましてかじりついた あのむっとするふところのなかのお乳」というのがある。  遠い記憶の糸をたどりながら、若葉に埋もれた母の墓前に香華をたむけていて、いつぞや知人の女性が語ってくれたことを思いだした。四十年前、彼女が嫁ぐ日の朝のことである。彼女は仏壇に両手を合せ、それから後に控えている両親の前に行って「ながいことお世話になりました」と頭を下げた。するとニガ虫をかみつぶしたような顔をしていた父親が急にウッと呻き声ももらして急いでハンカチを取り出して口を覆った。母親は泣かなかったが、その代わりにこう言ってくれた。「我慢せんでもいいから、いつでも帰っておいで」。 遠い記憶の糸をたどりながら、若葉に埋もれた母の墓前に香華をたむけていて、いつぞや知人の女性が語ってくれたことを思いだした。四十年前、彼女が嫁ぐ日の朝のことである。彼女は仏壇に両手を合せ、それから後に控えている両親の前に行って「ながいことお世話になりました」と頭を下げた。するとニガ虫をかみつぶしたような顔をしていた父親が急にウッと呻き声ももらして急いでハンカチを取り出して口を覆った。母親は泣かなかったが、その代わりにこう言ってくれた。「我慢せんでもいいから、いつでも帰っておいで」。この一言が陰に陽に彼女の一生を支えつづけてくれた。苦しいことがあって挫折しそうになると、この言葉を思いだして、自分には帰るところがあるのだと安心した。そして、いつでも帰れるのだから、もう少し、もう少しと辛抱するうちに還暦を迎えたのだと彼女は言った。 浄土に生まれた人はこの世に還ってきて、困っている人のところへ飛んでいってその人を励ますことができると経典にある。その不思議な力を神足通(神のように速い足)といっているが、彼女のお母さんは、挫折して気弱になっている娘のところに浄土から神足通で還ってきて危機の中の娘を救ったのだなと思った。 |
内外ともに暗い話題が多いので爽やかなはなしを一つ。 「驕れる白人と闘うために日本近代史」(文春文庫)の著者・松原久子氏は稀にみる気骨の人で、自信を失っている日本人を叱咤して国際的に活躍している学者だが、アメリカ住いの氏が帰国したある日のこと。 氏は大阪で買物をして駅近くのレストランで食事をした。帰宅してその日の収支を計算してみると千円足りない。考えてみたが思い出せないので、あきらめることにした。三日たってから氏はまた大阪へ出て前と同じレストランで食事をした。すると一人の若いウェイトレスが氏のテーブルに走ってきて、あなたは三日前にここで食事をした時、自分が間違えて千円少なくお釣を渡してしまった方ではないかと尋ねた。彼女の話によると、仕事が終ってその日の締めを集計すると伝票の会計より千円多い。そこで伝票に書かれた時間と合計金額から、間違えたのは何時頃の何番テーブルのお客さんだったことが判明したという。彼女は深く詫び、もう一度出会えたことをとても喜んだ。 話をきいて私は伝教大師の「一隅を照す者を国宝という」という言葉を思いだした。黙っていればわからぬものを。これは一重に誇りの問題だと氏は言っている。どんな仕事でも彼女のように誇りをもって打ちこんでいる人が国宝である。 最近、日本は危ないという声をきく。子供にテストでよい成績をとれとはいうが、嘘をつくな、誇りをもてという声が少いのと無関係ではないのではなかろうか。 |
『奇跡のリンゴ』(幻冬舎刊)という本が今、話題になっている。青森県の特異なリンゴ農家の記録である。  この農園では農薬をやらないし、雑草も刈らず、肥料もやらない。農薬を全く使わないというのも画期的だが、肥料をやらないというのが面白い。肥料をやらないと木は養分を摂ろうとして一生懸命、根を伸す。それが結果として丈夫で寿命の長い木を育てることになる。また、この農園では土地を耕さない。耕すと表土が流され、「大地の腸」といわれて土壌をほどよく耕してくれるミミズが死ぬからである。こうした“非常識”なやり方でできたのが「奇跡のリンゴ」といわれるおいしいリンゴである。すべてのケースでこの方式が通るとは思えないが、今、米国農業の最先端で、無農薬、無肥料で耕やさずという古代さながらのやり方に熱い注目の目が注がれているというから、これは一度考えてみる価値があるのかもしれない。 この農園では農薬をやらないし、雑草も刈らず、肥料もやらない。農薬を全く使わないというのも画期的だが、肥料をやらないというのが面白い。肥料をやらないと木は養分を摂ろうとして一生懸命、根を伸す。それが結果として丈夫で寿命の長い木を育てることになる。また、この農園では土地を耕さない。耕すと表土が流され、「大地の腸」といわれて土壌をほどよく耕してくれるミミズが死ぬからである。こうした“非常識”なやり方でできたのが「奇跡のリンゴ」といわれるおいしいリンゴである。すべてのケースでこの方式が通るとは思えないが、今、米国農業の最先端で、無農薬、無肥料で耕やさずという古代さながらのやり方に熱い注目の目が注がれているというから、これは一度考えてみる価値があるのかもしれない。この話を知って思ったのは、今の子供のことである。あまりにも肥料たっぷりに育てられているから根がよく張っていないのではないか。しばしば指摘されていることだが、長生きできるのは若いころ貧乏を知っている世代くらいかもしれない。仏教でこの世を娑婆というのは梵語のサーハから出たもので訳せば「忍土」となる。忍耐しなければ生きていけぬ世界という意味である。リンゴは苦悩に耐えておいしい果実となる。忍耐のない人生だと人は人間になれない。 |
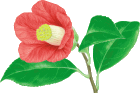 花便りがぼつぼつ聞かれるころになった。山寺の裏山には寒椿が咲いて枯木の山に風情をそえている。白梅も一輪一輪と開きはじめて、かすかな芳香を放っている。水仙も咲きはじめた。沖縄では早々と桜も咲きはじめたとニュースにあった。 花便りがぼつぼつ聞かれるころになった。山寺の裏山には寒椿が咲いて枯木の山に風情をそえている。白梅も一輪一輪と開きはじめて、かすかな芳香を放っている。水仙も咲きはじめた。沖縄では早々と桜も咲きはじめたとニュースにあった。こうして咲く花にも無言のルールがあて、桜は梅のあとに咲きはじめ、紫陽花は桜のあとに咲く。花は決して順序を違えない。 また、冬の寒さの中に咲く花は、どの花も寿命が長くなかなか散らない。庭の山茶花などは11月頃咲きはじめてまだ延々と咲いている。これに比べて晩春から初夏にかけて咲く牡丹や芍薬などは、「花は愛惜のうちに散る」と詩人が詠んでいるように、あっという間に散ってしまう。これは冬には蜂や蝶が少なくて花粉の媒介ができにくいから開花が長く、春はそれらがすぐ飛んでくるので花は早く散っても受精は完了しているからである。
|
 中風のお姑さんの下の世話をしていたお嫁さんが、「看病の三年間は毎日、今日で最後、これで最後と自分で自分にいいきかせてやってきました」と言うのを聞いて、正受老人のことを思いだしました。信州飯山に庵を結んで悟道三昧の修業に明け暮れた禅の高僧ですが、禅師に「一日ぐらし」という教えがあります。その概要はこうです。 中風のお姑さんの下の世話をしていたお嫁さんが、「看病の三年間は毎日、今日で最後、これで最後と自分で自分にいいきかせてやってきました」と言うのを聞いて、正受老人のことを思いだしました。信州飯山に庵を結んで悟道三昧の修業に明け暮れた禅の高僧ですが、禅師に「一日ぐらし」という教えがあります。その概要はこうです。
一日ぐらしの要領で、今年がよい歳になりますように。 |
あちこちで老人いじめの話を聞く。寝たきり老人のおむつを替えながら「よく食べるから汚い」と露骨に言ったり、無事に退院して帰ってきた老人を「また元気になったんだよね」と仲間で喋っているというような話である。  たしかにおむつの交換は汚いだろうし、邪魔な老人が再び元気になった姿を見てガッカリする気持ちもわからないではないが、順番に年をとっていくのだから、もっと視点をかえて老人をみることはできないものだろうか。それを転換させる方法が信仰という観念ではないかと思う。 たしかにおむつの交換は汚いだろうし、邪魔な老人が再び元気になった姿を見てガッカリする気持ちもわからないではないが、順番に年をとっていくのだから、もっと視点をかえて老人をみることはできないものだろうか。それを転換させる方法が信仰という観念ではないかと思う。全ゆる仏さまの中で人気随一の仏さまといえば観音さまで、それは慈悲を第一とした仏さまだからである。その観音さまは衆生済度のために三十三通りに変身するから三十三観音といわれている。その中には障害者もいるし。病人や死にかけた人もいるし、蛇や魚までいる。だから老人の本体は仏さまで、目の前にいる老人は仏さまの変身した姿であると思うのであうる。マザー・テレサにも、 「あなたに必要とされていない人は変装した神なのです」というような言葉があったように思う。 世の中には神や仏など信じない人が沢山いるから、今、目の前にいる人が仏の変身した姿、神の変装した姿だというと、何を寝言を言うかということになるだろうが、少なくとも、そんな見方があるのだと知れば、老人をみる見方が、それだけ豊かになることだけは間違いないと思うのだが、どうだろうか。 |
勘のいい目のみえない人に会って『盤珪禅師語録』の中に出てくる盲人のことを思いだしました。江戸初期、播磨の国(兵庫県)に実在した人で、この人は人の話声を聞いて、その人の心中を見抜いたといわれています。この人は常々、 「賀詞には必ず愁声あり。弔辞には必ず歓声あり」  と言っていたそうです。祝い事があったので相手に「おめでとう」と賀詞を言っているのに、心はそのようになっていない。「うまいことをやりおったな」という、そねみ、ねたみのようなものが声音から感じられる。 と言っていたそうです。祝い事があったので相手に「おめでとう」と賀詞を言っているのに、心はそのようになっていない。「うまいことをやりおったな」という、そねみ、ねたみのようなものが声音から感じられる。反対に「お気の毒に」と弔辞をいいながら、「いつも偉そうにしているからバチが当ったんだ」というような歓声が声音の中に感じられると言っているのです。 そしてその盲人が盤珪禅師のことを、 「盤珪さんだけはそんなことがない。いつ聞いても、おめでとうと言っている時は心の底から心が喜びに満ちていることが声音でもわかる。反対に気の毒にと言っている時も同様。これでくい違いのあったことが一度もない」と言っている。 盲人は盤珪さんこそ真の禅者だと言っているのですが、それにしても恐ろしいぐらいの鋭い勘ばたらきです。私たちはいつも何をしていても自分のことを中心にして考えています。宮沢賢治は「アラユルコトヲ、ジブンヲカンジョウニイレズニ」と言っていますが、その言葉に照すと恥ずかしいくらいです。 勘のいい盲人と話しながら、自分が恥ずかしくなるばかりでした。 |
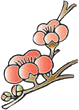 高齢者が増えるにつれてボケる人も増えてきた。八十歳以上では四人に一人がボケると聞けば、これは人の話ではない。 高齢者が増えるにつれてボケる人も増えてきた。八十歳以上では四人に一人がボケると聞けば、これは人の話ではない。知り合いのお婆さんが亡くなった。気丈な人だったが、ボケが始まると財布を盗られた、判子を盗られたと言いだした。人聞きがよくないのでその家のお嫁さんは、「私は盗ってないよ」といい返す。そして更に自分の袋をもってきて開いて見せて、「ほら、無いでしょう」と確かめさせる。それだけならよくある話だが、このお嫁さんの有難いのは、「お婆ちゃん、それはどこかに置き忘れたんだよ。私も捜してあげるから一緒に捜そう」といって時間をかけて二人で家中を捜しまわることである。そうしているうちにお婆さんは疲れてしまって、「もういい、私がどこかに置き忘れたんだろう」となって一件は落着する。そんなことが、しょっちゅうだったというからお嫁さんの辛棒づよさには脱帽だ。 ボケは家庭内に不安が多く、その上に家族からも尊敬されず、過去の業績は無視され、立場を失った喪失感から始まるといわれている。だからボケにかかった老人には、なでる、語りかける、ほめるなどして相手に存在感を感じさせてあげることが大切で、叱ったりすることはマイナスになる。 「同事」というのは菩薩さまが実践する慈悲行のことで、相手の気持ちと一緒になって相手を安心させてあげることである。お嫁さんがお婆さんと一緒になって捜しものをしてあげたのは同事という菩薩行を実践したことになる。 |
昔、滋賀県彦根に豆腐づくりの神様のような人がいました。親父は一日に三箱しかつくらない。しかし、その三箱に全力を注ぎました。 だからその豆腐はおいしくて、開店するとすぐに売り切れました。 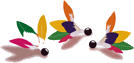 何人もの人から、「もっとつくったらどうか。店を大きくするなら加勢しよう」といわれましたが、親父は頑として聞き入れなかった。 何人もの人から、「もっとつくったらどうか。店を大きくするなら加勢しよう」といわれましたが、親父は頑として聞き入れなかった。「これでよいのです。これ以上手を拡げると、つい粗末なものをつくりかねませんから」と言って黙々として豆腐をつくりつづけ、人から「うまい、うまい」と褒められることを生き甲斐として豆腐づくりに専念して一生をおわったそうです。 昨年は食品問題で騒がれ、一年を締めくくる文字は「偽」でした。 その対極にあるゆな生涯をおくったのがこの豆腐屋さんですが、見事なものです。こんな人を身のほどを知る人、分際を知る人というのでしょう。身のほど以上のものに手を出して墓穴を掘る結果になる。人の世の苦しみや悲しみは、みなここから芽生えてくるようです。 無量寿経の「汝自当知」(汝自ら当に知るべし)は、言葉をかえていえば身のほどを知れということで、人間の永遠の課題を示してくれたものだと思います。 |
やがて春の彼岸の入りがくる。彼岸という言葉は龍樹(世紀前150〜250)の「大智度論」に、「生死をもって此岸となし、涅槃をもって彼岸となす」とあるのが最初であるとされる。小林一茶は 今日彼岸さとりの種をまこうかな と詠んでいるが、彼岸の本質がよくいい表されている。 「さとり」とは「さようとる」から出ているといわれる。事実を事実として逃げまわらずに、ハイッと素直に受けとることが、さとりである。前に進む力は、そこから授けられている。 古林泰子さんは足に障がいをもって生まれた人だが、下は彼女の詩。 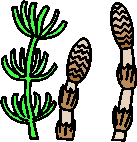 歩きながら考える 歩きながら考える急いで通りすぎた人の 気づかなかった野の花が見える 草が語りかけてくる 私にふりそそぐ太陽の愛 走れなくてよかった 決して人の後を歩んでいるのではない 前へ前へ わが歩みに心をこめて悔いなく 詩の後で泰子さんは、「毎日冷たいコルセットをはずす時、今日も一日すばらしかったと感謝する。もし満足な足で生まれていたら、私自身つまらぬ人生を歩んでいたかもしれない。決してあきらめではない。これからも精一杯生きたい。動かない足であることに喜びを感じて」と述べている。 このような条件がととのったら感謝しようでは、いつまでたっても感謝できる日はこない。昨日は過ぎた、明日はまだ来ない。あるのは今だけ。ただ今ただ今。 |