|
|
|
|
年末になって今年も「喪中につき年賀欠礼」のお知らせを何通かいただいた。 忌中の家族の皆さんには、淋しい正月を迎えられることだろう。ご挨拶をいただいて、いつの日か自分も同様のハガキを書き、また自分のために家族の者が書く日のくることを思う。思えば愛しい者との別離ほど、せつないものはない。 あきらめよ 天の星さえ会者定離 というけれど、頭ではわかっていても情ではあきらめきれないのが人間だ。  九十をすぎて元気な老夫婦がいるので、「幸せですね」と奥さんに言うと、「皆さんがそのように言って下さいますが、この年ですから、いずれどちらかが先に往かねばなりません。一人残るのはいやだ、あんたが先に往ってよ、と言い合っている毎日なんですよ」という答えであった。 九十をすぎて元気な老夫婦がいるので、「幸せですね」と奥さんに言うと、「皆さんがそのように言って下さいますが、この年ですから、いずれどちらかが先に往かねばなりません。一人残るのはいやだ、あんたが先に往ってよ、と言い合っている毎日なんですよ」という答えであった。別れは悲しいけれど、浄土の教えを尊ぶ人には再会がある。 法然上人は晩年、法難にあわれて御流罪になる時、別れを惜しむ弟子に、 「宿縁むなしからずば同一蓮に座せん。浄土の再会はなはだ近きにあり。今の別れはしばしの悲しみ、春の夜の夢のごとし」と諭されている。 山崎弁栄上人は母との別れに臨んで詠んでおられる。 「しばしまた別るるもののやがてゆく 西の都に会う日をぞ待つ」 愛しい家族の人が先立っていった悲しみを、一足先に浄土に往って待ってくれている人になったのだと思いとって、今日を力強く歩んでいきましょう。 |
少子化のうえ最近の若者は養子を嫌うので、後継者に困っている家が多い。そんな中で、めでたく養子縁組が整って双方とも喜んでいる家がある。だが最初は、やはり若者の抵抗があった。話をきりだしたのは青年の父だが、「あの家に養子にいけ」と言うと、「親父、米糠三号あったら養子にいくなと昔から言うじゃないか」と横を向かれた。そんな息子に向って父が言った。 「お前はこの家で生れて大きくなったが、もともとはあの家で生れたんだよ。往くのじゃなく還るのだ」 考えていた青年は、この一言で、なんとなくその気になったのだという。  この話を聞いて、人生の坂を越える要領は、これだなと思った。法然上人に「浄土という世界は有る無しの論議をして決める世界ではなく、有ると思いとっていく世界だ」という言葉があるが、事実は変らなくとも、それをどのように思いとっていくかが人生の明暗を分ける。 この話を聞いて、人生の坂を越える要領は、これだなと思った。法然上人に「浄土という世界は有る無しの論議をして決める世界ではなく、有ると思いとっていく世界だ」という言葉があるが、事実は変らなくとも、それをどのように思いとっていくかが人生の明暗を分ける。東北の覇者・伊達政宗は名高い遺言を子孫に残している。それは 「この世に客にきたと思えば何の苦もなし。朝夕の食事は、うまからずともほめて食うべし。元来、客の身なれば好き嫌いは申されまじ」 というものであるが、政宗の言うように、この世に客に来たと思えば、たいがいのことは安らかに受け流すことができる。 宗教とは人生に疑問を感じた時、それを意義づけてくれるものである。 |
残暑も日に日に薄らいで秋の彼岸が近づいてきた。彼岸とはインドの竜樹の大智度論に「生死をもって此岸となし、涅槃をもって彼岸となす」という句によったものである。此岸とは迷いの世界、涅槃とはその迷いが吹き消された世界のことである。 最近、人から聞いた話だが、ある家の老婆が三度目の入院を無事に終えて家に帰ってきた。近所の仲良しが祝いに来て「よかったね」と言うのを聞いて、傍らにいた家の坊やが、「でもうちのママはそう言ってなかったよ。『三度も入院してまた元気になって帰ってきたんだから』と言っていたよ」と言った。仲良しはハッと困ったことになったと思ったそうだが、そのとき老婆が、 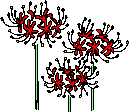 「そうかい、今度も元気で帰ってきたと言ってくれたのかい、うれしいね」 「そうかい、今度も元気で帰ってきたと言ってくれたのかい、うれしいね」と、こともなげに答えたのでホッとしたという。 観音経には衆生救済のため観音菩薩は三十三通りに変身すると説かれているが、その中には恐ろしい鬼となって毒舌を吐く菩薩となることもある。作家の吉川英治先生が座右の銘としたという「吾以外皆吾師」を鏡としたら、彼岸の世界は向うの方から、こちらにやってくる。 たとえ自分は此岸にいても、彼岸の人をみて、結構だな、自分もそうなりたいと願うことができたら、その人もまた彼岸の人になったのだと仏は説かれている。 なんとおおらかな教えだろうか。 |
お盆が近づいた。近頃はお盆といえばレジャーを楽しむ期間のようになっているが、ルーツは推古天皇の1400年前から始まったもので、インドのサンスクリット語のウランバーナが盂蘭盆となり、略してお盆となったものである。ウランバーナは「倒懸」と訳され、逆さまに吊されたような苦しみをいう。亡き人で、そのような苦を受けている人がいれば、その苦を免れてもらいたいと願い、生きている人で、ものの見方が狂っているため苦しんでいる人がいれば、正見にたちかえっていきたいと自分を省みる日がお盆である。 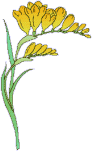 「幸福の物差」はお金だから、貯金通帳の帳じりが増えるほど幸せになれると決めている人がいる。たしかにお金は大事なものだが、それだけでは幸せになれない。女性の好むナイロン靴下を開発したのはアメリカのカロザースという天才科学者である。それを売り出したデュポン社は一躍大企業になったが、会社は彼の御機嫌を損じては大変と破格の給料を与え、その上、世界中のどんなホテルに泊ろうが、どんな高級レストランで食事をしようが、費用はすべて会社もちという特典を与えた。その彼が41才の時、宿泊先のホテルで服毒自殺をした。机上には「生甲斐がなくなった」という遺書が残されていた。社会学者・デュルケムは、自殺者は貧乏人より金持に多いことを論証している。 「幸福の物差」はお金だから、貯金通帳の帳じりが増えるほど幸せになれると決めている人がいる。たしかにお金は大事なものだが、それだけでは幸せになれない。女性の好むナイロン靴下を開発したのはアメリカのカロザースという天才科学者である。それを売り出したデュポン社は一躍大企業になったが、会社は彼の御機嫌を損じては大変と破格の給料を与え、その上、世界中のどんなホテルに泊ろうが、どんな高級レストランで食事をしようが、費用はすべて会社もちという特典を与えた。その彼が41才の時、宿泊先のホテルで服毒自殺をした。机上には「生甲斐がなくなった」という遺書が残されていた。社会学者・デュルケムは、自殺者は貧乏人より金持に多いことを論証している。「喜足小欲」(足るを喜こび小欲である)こそ幸せの源泉であったと正見することが倒懸の苦から免れる道であり、それがお盆の精神だろう。 |