|
|
|
|
今年の春、腰部脊柱管狭窄症を患って歩行が困難になってから、星野富弘氏のことをよく思い出しています。氏は学校を出て体育教師になった直後、クラブ活動中にマットの上に墜落して頸随を損傷してから両手足の動かぬ人になった。以来、特殊な車椅子に乗り、口に筆をふくんで詩画を創作しておられる。 氏はベッドの上で将来のことを思い悩んでいたとき、幼いころ、近くの川で遊んでいた時のことをふと思いだした。やっと犬掻きができる程度だった星野さんは、深いところへ行かないようにしていたが、ふと気づいたら水の流れに巻き込まれていた。手足をばたつかせて岸辺に戻ろうとしたが、ますます深みにはまりこんでいく。もう死ぬかと思ったとき、声なき声が全身を包んだ。「もう元の岸にもどらなくてもいいぞ」という声だった。その声を聞いてから星野さんは、水に身をまかせて身を反転させて下流に泳いだ。すると不思議なことに自分を飲み込もうとしていた川が、いつもの穏やかな川に戻っていた。そこで立ち上ってみると、足が川底に届いたそうです。 そのことを思い出して、「そうか、元に戻れなくともいいのだ。今できることを精一杯していこう」というのが星野さんの生きかたになった。 「動ける人が動かないでいるには忍耐が必要だ 私のように動けない者が動けないのに忍耐など必要だろうか そう気づいたとき私の身体をギリギリに縛りつけていた忍耐という刺のはえた縄がフッと解けたような気がした。」 |
『君の名は』で有名な作家の菊田一夫氏は孤児で育って、一日一食の牛めしで生活していた。そんなある日のこと、飯を食って立とうとしたが腹がへっていて立てない。仕方なくノロノロと立ち上がろうとすると、それを見ていた食堂の親父さんが黙って近づいてきて一杯の牛めしを出してくれた。 「今夜は売れゆきが悪くて飯が余って困っているんだ。腐らせるともったいないからね・・・」。それがその時の親父さんの一言だった。 少年は夢中で食べて外へ出た。(この真冬に飯が腐るものか。それに売れゆきが悪いなんて、そんなことがあるものか。評判の飯屋だということが知っているぞ)・・・少年は店の中の親父に怒鳴ってやりたかったが、気持とは裏腹に無性に涙が出て、泣きながら走って帰っていったという。一夫さんは晩年、著書の中で「私の文学者としての原点はあの日の牛めし屋の親父さんの一言だった」と語っています。 その夜の思い出が深く一夫さんの心に刻まれたのは、親父さんの人を傷つけまいとする心使いの一言だった。雑宝蔵経という経典には、どんなに貧しい人でも七つの布施ができるといっており、これを「無財の七施」といっている。その中に「心慮施」という布施がある。これは相手の人の気持を考えて言うてあげる言葉の布施で、こんな布施には「愛語よく回天の奇蹟を生ずる」といって、死にかけた者を生き返らせるような力がある。 |
福岡のお寺にいくと座敷の床の間に般若心経の写経が掛けられていて、大石順教拝写と署名がある。両手のない彼女が口に筆をくわえて書いたものだった。思わず合掌礼拝、改めてウーンと唸るより外なかった。 思えば彼女の運命ほど数奇に満ちたものはなかった。十六才の時、大阪の芸者屋に養女にもらわれてきていたが、ある日、養父が突然発狂して七人の芸者さんを次々に斬殺した。少女だった彼女だけが両腕を切られただけで血の海の中にいるのを辛うじて救出された。しかし突然障害者になって前途は真暗だった。生きるために旅役者になっていたある日の朝、腕がないので洗面器に顔を浸して洗顔していると上の方で小鳥の声がする。ふとみると番のカナリヤが鳥籠の中でひなに口で餌を食べさせている。その姿をじっと見て彼女の心の中に静かな爆発がおこった。手のない小鳥がああして子育てをしている。両手がないからといって泣いてばかりではいけない、私にもなにかできることがあるはずだ。それから彼女は口に筆をくわえて字の稽古をはじめ、後年、遂に権威のある筋から特賞をうけるまでになったのです。 「口に筆とりて書けよと教えたる鳥こそ我身の師にてありける」 旅先の木賃宿で書けよと教えてくれた小鳥こそ私の先生だったと言っているのです。生きる道は与えられているのです、ただそれを発見できないでいるだけです。そういう尼の無言の説法を写経の中に聞く思いだった。 |
川崎市の中学一年・上村遼太郎君殺害事件は衝撃的でした。死んだ蝉を手にして「これは電池が切れている」といった子供がいたそうですが、両者に共通するのは、現代人の寒々とした心の光景です。 小林一茶に「やれ打つな蝿が手をする足をする」という句があります。一茶は蝿を叩こうとしたら、蝿が手足をこするのが命ごいをするようにみえたので打つのをやめたのです。このような小さな命にも心をよせて愛情をふり注ぐという深い心は、もはや現代人から失われてしまったのでしょうか。 深い信仰に生きた人として名高い荒巻くめさん(1854〜1925)の家へ真夏の早朝、知人が所用で尋ねると、くめさんは「かゆい、かゆい」と全身を掻いている。知人が「どうしたの」と聞くと、彼女は声を落して「人に言うて下さるなよ」と念を押して、「実は昨夜は一晩中裸になってお念仏していたのです」。知人が驚いて「どうしてそんな無茶なことしたの」と聞くと、「私がお念仏している時の血を蚊が吸うと、それがご縁で蚊が今度生れてくる時は仏縁のある者に生れ代ってこられるのじゃないかと思ってね」 現代人の感覚からすれば、一茶やくめさんの行為は、まことに馬鹿げたことでしょう。しかし二人を笑う合理主義者の生きざまから人生の幸福は生れてくるでしょうか。この二人の一見愚かしいとも思える至純の心は、現代人の心の隙間を突く頂門の一針ではないでしょうか。 |
暑さ寒さも彼岸まで。18日から彼岸に入るが、一週間つづくお彼岸のお中日の「中」には、片寄らないという意味もあるが、命中の中で、中道即ち人間の歩む道にピタリと当るという意味もある。 現実の生活は苦しい。いやなことが多い此岸だからこそ幸せの理想の彼岸が望まれる。その彼岸へ渡る方法が六ツあるが、その第一が布施である。それは一般には物や金を施すことだと考えられているが、形のない布施もある。言葉も立派な布施で、それを言辞施という。 先日テレビで日本には謝罪業という珍しいビジネスがあることを知った。相手に謝罪する場合、本人に代ってただひたすらに詫びることを業務とするビジネスである。こんなビジネスは決して成り立たないのがアメリカ。過失が明らかな場合でも、当事者は決して謝らない。謝ればそれが裁判に反映されて不利になるからである。だから訴訟国家といわれるように訴訟沙汰が多く、これでアメリカは潰れるのではないかとさえいわれている。そこで、「相手が詫びたらどうするか」という質問をしてアンケートをとってみたら、三分の二の人が訴訟をとりさげると答えた。そこで「アイム・ソーリ法」(すみません法)という法律ができた。「すみません」といっても、その言葉は裁判に反映されないというものです。 日本は世界で一番「すみません」という国だと言われているが、そんな布施ができるのは、日本の美点といってもよいのではないでしょうか。 |
大毘娑婆論というインドの本にこんな話がある。 貧しい一人暮らしの青年があって、朝夕、神に幸せを授けたまえと祈っていた。 するとある日、目のさめるような美女がきて、「あなたの祈りが届いたからやってきた。私は吉祥という幸福の女神です。中に入れてください。」という。青年は喜んで中に入れようとすると、その後から二目とみられぬ醜女が続いて入ってこようとする。青年が吉祥に「これはどんな人ですか」と聞くと、「それは私の妹で不幸の女神で黒耳と申します」と言う。青年が「姉さんのあなただけが入って妹は帰らせてください」と頼むと、「いいえ、それはできないのです。姉の私と妹は影と形のようなもので、離れることができないのです。どうしても妹はいやだというのなら私も出ていきます。どうしましょうか」と言う。青年は答えがみつからず途方にくれてしまった。 人間の幸不幸は一心同体のもので、区別できないということを物語るものです。 「自分たちの仲間以外はみな敵」「敵は殺すことが正義」「日本の悪夢がはじまる」 ―中東の過激思想の台頭で暗雲がたちこめている。だが一人の女神だけを選ぶことができないと知って、受けねばならぬものは素直に受けていきたい。 仏教ではこの世のことを娑婆世界という。サハーというインドの言葉の音与で、訳せば「忍土」となる。苦しみが多く、耐え忍ばねば一日も生きていけない世界という意味。忍土なのだからみな耐え忍んでいきたい。心を一つにして。 |
馬が退場して羊になりました。諸橋轍次博士の「十二支物語」によると、羊は史実や伝説が非常に多い動物のようです。これはその一つですが、楚の国に正直な若者がいて、あるとき彼の父が人の羊を盗ったので逮捕されました。すると彼は正直にそれを証言したそうです。ある人が彼の正直さを褒めるのを聞いた孔子は、 「私は彼を正直者とは思わない。仮に盗ったとしても、その時は、子は父のために隠し、父は子のために隠す。これを正直というのだ」 と述べています。 論語にある有名な説話ですが、昔から論争のあるところです。正義をとるか、親子の愛をとるかという問題です。日本の刑法は後者に重点が置かれているようですが、これは大事なことだと思います。いま日本は慰安婦等の歴史問題で誤解をうけて苦しい立場に追いこまれています。外国在住の日本の子女が性奴隷をつくった国の子孫として、いじめられたというような話もきこえてきます。 日本の過失の面を非難するあまり、あやふやな資料に依って誤報を流しつづけてきた結果がこれです。要するに孔子さまの正直の意味をとりちがえていたのです。 「父のために隠す」という心根は大事にしていきたいものです。 |
新しいカレンダーを頂く頃になりました。馬齢を重ねるにつれ「おのが死ぬ月日もあらん春暦」と詠んだ芭蕉の心境の一端をのぞいた気持で暦を見ています。 今年は親しくしていた学友が次々に逝って秋の風が一際身にしむ年でした。その一人は脳梗塞を患い、一言も発することなく、一滴の水も飲めないまま胃ろうで生きた三年間でした。先般お参りにいって奥様からいただいたお茶を飲みながら、故人はこれがどんなに飲みたかっただろうかと思いました。 阿弥陀経には浄土の住人たちの姿が描かれている。そこに住む人々は毎朝、花を盛る器にたくさんの花を盛って、十方の仏に供養して、それが済んだら帰ってきて食事をとると述べられている。 私どもは家庭において食事をつくった時や、よそから頂戴物をした時などは、まず仏壇に供えてから、しかるのちにいただくというのは、阿弥陀経に描かれている浄土の住人の真似をしていることになる。 浄土の住人は朝食の前に、まず十方の仏に供養するということですが、十方とは全世界という意味。広い世間には、食物がなくて飢え死した人、水を飲みたいと思いながら飲めずに死んだ人が多数いる。浄土の住人たちは、まずそんな人に供養するというのです。私たちも浄土の住人に習って、食事をする時には、飲食に思いを残して死んだ人のことを考え、「さあ一緒に食べよう、さあ一緒に飲もう」という気持を持ちたい。それが何よりの供養となる。 |
文部科学省所管の統計数理研究所が五年毎に実施している国民性調査によると、今回は「生れ変るなら日本か外国か」という設問に83%が「生れ変るなら日本」と答えている。特に若者の比率が高い。日本に対するこのような肯定的な回答が出るのは昭和28年に始った調査では初めてのことで、同研究所のセンター長は「震災時の秩序だった行動が国民意識に反映されたところが大きいのではないか」と分析している。思えば「慰安婦」などの問題で、日本は大きな誤解の中に沈んでいる。だから若者達は日本の未来に悲観的になっていたのではないかと思っていたのに、この結果は一条の光に遇った思いだった。 思えば震災時、日本人が無意識にとった行動は世界を驚かせた。 当時の雑誌に救援物資を届けたヘリコプターの外国人女性パイロットが一文を寄せている。彼女は着地するのが恐ろしかった。どこの国でも着地するとワーッと人が殺到してきて身の危険を感じるからである。日本の場合もそうなることを覚悟して着地したのだが、近づいてきたのは代表者である初老の老人一人だった。彼が「もらっていいかね」と彼女の許可を得てから、バケツリレーが始まった。しばらくすると、「もうこれで結構です」と紳士が言う。彼女が「なぜですか」と尋ねると、「私たちはこれで十分。あとは外の人に届けてあげてください」。 いざ、という時に道徳力を発揮する先祖の遺産を受け継いだ人々をみて、多くの若者が「生れ変るなら日本」という答えを選んだわけである。 |
入道雲が沸きたつような夏日がないまま、急ぎ足で秋がやってきたような感じの昨今です。今年の秋は大雨や土砂災害で各地に大きな被害がでましたが、しかしここ何年かは九州名物の強烈な風を伴う台風だけは、はずれて通過してくれるので有難い。「台風が来ないので有難いね」と人に話したら、その人が「台風も大事なんだよ」といってある学者の話をきかせてくれて感銘した。 その人の話によると、以前、原子力で台風の目を潰すことが考えられた一時期があったらしい。でも考えるだけで終っていたからいいので、もし実行されていたら日本列島は無人島になっていたかもしれない。台風が南方から運んでくる雨や熱が冷たく乾燥した北に運ばれてくるから、人がこんな島に生きられているのであって、台風がなくなると日本列島は寒くなり、水不足となって人は生きられなくなるという。 嫌なものも無ければ人は生きられない。人智をこえた自然の営みの中に生命の営みがつづいていることがわかる。思えばこの世は反対のものがあるからよい。プラスとマイナスがあるから電気が灯る。晴と雨があるから森羅万象が育つ。動く車輪と動かぬレールがあるから電車が目的地に着く。人間も一つの体の中に入口と出口が備っているから生きていける。 「月にも三日月あり、半月あり。されどもとはみな満月なり。佛さまなり」と気づくとき、自分勝手の目先の都合だけを考えて出ていた愚痴が止む。 |
横田めぐみさんは十三才の時、新潟から北朝鮮に拉致された。毎日泣き暮す少女を見て当局者は、「朝鮮語を勉強したら五年後に日本に帰す」と言った。少女は一生懸命勉強した。そして十八才になったので申し出ると拒否された。それなら監視下でいいから新潟へ行き、遠くから親の顔を見させてほしい、じっと見るだけでいいからと懇願したが、それも拒否された。それがきっかけとなり、めぐみさんは精神を病むようになり、病院に収容されたという。 これは当時、新聞に載った、自らめぐみさんを拉致し、後に韓国に亡命した元北朝鮮工作員の証言だが、気味のわるいほどリアリティにあふれている。 この世にこんな残酷、非道があるだろうか。涙なくして聞けない。 同じように拉致された人々の第一回調査報告が今月中に示される予定になっている。これを待つ肉親の期待と不安は、いかばかりだろうか。 十年ほど前、所用で行った山口市の駅の待合室で偶然、めぐみさんのご両親と並んで座り合わせた。支援者の集りで講演した帰りだと言っておられた。その節、母の佐紀江さんの一言が今も鮮やかに思いだされる。 「私たちは今でもめぐみが生きていることを信じて、こうして動きまわっているのです」。 「(親は)子が遠くへ行けば帰りてその顔を見るまで出でても入りてもこれを憶い、寝ても起きてもこれを憂う」と父母恩重経にある。娘不在の三十七年間のお二人を思う時、「遠行憶念」という親心を表す言葉を思いだします。 |
五十六才で亡くなった戦争未亡人の五十回忌が営れた。夫は十二才を頭に五人の子を妻に託して征った。それから「母は強し」の言葉通りの、なりふり構わぬ妻の闘いが始まった。その彼女が私に一度だけ涙をみせたことを思い出した。それは、「あなたの夫はなぜ戦争に行ったのか」と人から言れた時のことである。彼女にはそれが夫を非難する声に聞えたのである。 戦争は「悪いのは一部の軍国主義者、国民はその被害者」という時代になった。おかげで国民はみな善人になれたが、その代り軍人はみな軍国主義者の手先、従ってその死は犬死となり、巧妙に徴兵をのがれた者は成功者となった。ところが経済的に日本が復興してくると、世間の言い方はガラリと変った。「あなたが死んでくれたおかげでこの繁栄がある。やすらかにおやすみ下さい。」 毎年八月十五日がくると、「あやまちはくり返しません」という声が聞えてくる。英霊たちは、それをどんな気持ちで聞いているのだろうか。「オレ達は親や妻子を護りたかっただけなのに・・・」と呟く声が聞えてくる気がする。 あわれ英霊よ、生きている時は国の華ともちあげられ、死ねば犬死となり、景気がよくなれば「あなたのおかげ」とおだてられ、夏がくればあやまちだったと責められる。英霊の皆さんには居心地のいい日本ではないでしょうが、でもお盆だから帰ってきて下さい。あなたを待っている人もいるのです。 「かくばかり醜き国になりたるか 捧げし人のただ惜しまるる」(戦争未亡人) |
毎年「夏のつどい」に山寺へ来る子供たちの夜のおたのしみは、幽霊ばなしを聞くことである。そこで常々幽霊には関心をもっているのだが、日本の幽霊の特徴は若い女だと聞いている。まず長い髪を、うしろへ長くひいている。これは済んでしまったことを未練たらたらと引きずっていることを表している。 次は両手を前に垂している。これは、実際に来るかどうかわからない未来の心配事をくよくよととりこし苦労して悩んでいることを表している。 次は足がないということ。これは過ぎ去った過去や、まだ来ない未来に心が縛りつけられて、肝心の「今」が忘れられていることを表している。 「過ぎ去れるものを追うことなかれ、いまだに来たらざるものをねがうなかれ、ただ今日なすべきことを心してなせ」(新訳仏教聖典) ・・・・夏の夜を賑わす幽霊も釈尊のご説法を表す姿だったことがわかる。 某寺の有名な幽霊絵を二人のお婆ちゃんが参観に行った。幽霊のうらみ、つらみのすさましい眼をみて、一人のお婆ちゃんは、「あれは嫁の眼だ」とつぶやいた。もう一人のお婆ちゃんは、「私はあんな眼で嫁さんを見ていたのかなあ」とつぶやいた。これを「一水四見」という。同じ池の水でも人間が見れば飲み水と見え、魚がみれば住家と見え、天女が見れば宝石が敷きつめられていると見え、餓鬼がみれば血膿がたまっているように見える。幽霊を見て、あれは自分の姿かもしれないと思えたら、その人は仏の光に照らされたことになる。 |
子供を十三人生んだ母の五十回忌の法要がつとまった。生き残りの子供たちも少なくなっていたが、そのうちの一人が言った。 「五月の大型連休で家の若い者親子四人が海外旅行に行きました。私は見送りながら、孫のことで内心複雑な思いでした。親に甲斐性があるから、孫はいつでも行きたいところに連れていってもらえるし、欲しいものも買ってもらえる。世の中そんなものだと思って大きくなると、長い一生の間には借金に追われるような日がくるかもしれない。その時どうなるのだろうか。ブレーキのきかない人間に育っているから、その時は、みじめでしょう。それに比べて私なんか貧しい上に兄弟が多いから、親は苦労しました。たまに買ってくれる菓子は兄弟で分けあって食べましたが、その一口の菓子のおいしさが忘れられません。わずかな菓子に幸せを感じることができたのも、貧しい家と兄弟のお蔭です」。 話に耳を傾けながら、私は十八世紀の思想家ルソーの言葉を思い出しました。 「子供たちを間違いなく不幸にする唯一の方法は、いつでも欲しいものは買って与え、行きたいところに連れていってやることだ」『エミール』 五月末、NHKスペシャルで「エネルギーの奔流」−破局は避けられるか−が三回連続で放映された。エネルギーを浪費しつづける人類の暗い未来を予測したものですが、アナウンサーの最後の一言が印象的でした。それは「生きのびたいと思うなら少欲知足という原点にたち返るしかない」という意味のものでした。 |
小学校の同級生で地元にいる者が次々にガンになり、私自身も去年の暮、膀胱ガンを宣告され、おそまきながら彼等の仲間入りをさせてもらいました。 四月初旬、そのガン爺さんばかり四人が山寺の桜の下に集って、ささやかなクラス会をしました。みんな自分の運命がよくわかっている者ばかり。かえってサバサバして和気あいあいの楽しい集いになりました。 現在はガンになると告知することが普通になっていますが、それがいいかわるいかわからない。後で医者が訴えられないための用心だとも聞いています。 だが考えてもれば、仏教徒はみな既に死の告知を受けているようなものです。 釈尊は「この世において、どんな人もなしとげられないものが五つある」といって、その一つに死があげられている。これはまぎれもなく仏の死の告知です。続いて「世の人びとは、この避けがたいことにつき当り、いたずらに苦しみ悩むが、仏の教えを受けた人は、避けがたいことは避けがたいと知るから、このような悩みをいだくことはない」と述べられている(新訳仏教聖典)。 死刑囚とよばれる人がいますが、死刑囚でなくとも、処刑の期日が決ってないだけで、身分は同じであることに変りはありません。 たまわりし処刑日までのいのちなり 心素直に生きねばならぬ これは死刑囚・島秋人の遺歌ですが、万朶の花の下で友人と杯を酌み交しながら、しきりに思いだされたのが、この歌でした。 |
公務員の人事異動が新聞を賑わせています。念願どうりの栄転で祝杯をあげている人もいるだろうし、ガッカリしている人もいるだろう。沢山の名前の中から笑い声と溜め息が聞えてくるようです。 元東芝会長に岩田弐男という人がいました。非常に有能な人で、皆から将来を嘱望されていたが、昇進を目前に突然地方の工場に左遷されてしまった。それから懊悩が始まった。いっそ会社を辞めてしまおうかと思ったことも何度かあった。彼は趣味として俳句をやっていたが、そのころの句に 熱燗や あえて職場の苦はいわず というのがある。当時の彼の心情がよく現れている。好きな一杯をやりながら、ともすれば出そうになる愚痴をぐっと我慢しているのです。そして悩んで時間が経つうちに心境が変わってきた。権謀術数は世の常ではないか、自分はそれに対処できなかっただけだ、家族もいる、サラリーマンをやめて自分に何ができるか、この職場で精一杯やるより外にないではないかと。その頃の心境が句になった。 熱燗や すでに左遷の地を愛す 彼はすでに気持が整理できて、左遷の地を愛する人になっていたのです。彼が後に会長の座に昇りつめたわけが、よくわかるような気がする句です。 彼がそのようになった心境を禅語では「随所に主となる」(どこにいっても主人公になる)といい、念仏では「往生する」(往って生きる)といっている。 |
有害な濃霧が日本に押し寄せてくるニュースを聞いて、思いだした話がある。 岡崎女子大の宇野正一先生は、家庭の事情で祖父母に育てられた。祖父は昔の人らしく食物には仏さまがござるから粗末にしないようにといつも孫に教えてきた。宇野さんが小学校5年時、学校に顕微鏡がきて、先生がそれでいろんなものを見せてくれた。そこで宇野さんは、いつも祖父かがあのように言っているので、ご飯粒の中にはどんな仏さまがいるのかと思って顕微鏡にかけてみたが、なにも見えない。そこで先生にたずねたら、「米粒の中にはそんなものはいないよ、君のおじいさんは迷信家だね」と笑われた。 そこで宇野さんは家に帰ると早速、「おじいちゃんの嘘つき」と祖父をなじった。すると祖父は、何も言わずに仏壇の前に座って泣きだした。宇野さんは後年、「その時の祖父の後姿が忘れられない。今にして祖父の教えが身にしみてわかる。今我々が忘れているのは、この祖父のものの見方なのだ」と言っている。 歩くとき、両足を同時に前に出して前進することはできない。交互に出して初めて調和が保てて前進できる。人間の社会も同じことで、現在は科学的合理主義が進んで外面は豊かになったが、内面がついていかないため、人間の存在さえ危ぶまれる状態になった。米粒の中に仏がござるなど非合理の極みだが、それが人間を深めてきたことが忘れられている。大いなるものへの畏怖を忘れた象徴がこの濃霧ではなかろうか。 |
毎年賀状を書くころになるとお世話になるのが諸橋轍次「十二支物語」。今年も開いてみると、馬には沢山の逸話があることに気づく。それだけ人間と深いかかわりがあったということでしょう。中でも名高いのが「人間万事塞翁が馬」です。 昔、北方の塞(とりで)に済んでいた翁の馬が胡国へ逃げていったので、人々が悔みを言うと、老人は平気な顔で「これが幸せになるかもしれない」と言う。果してその馬が沢山の駿馬を連れて帰ってきた。「よかったね」と人々が言うと、翁は「これが禍いの種になるかもしれぬ」と浮かぬ顔。そのうち翁の息子が駿馬から堕ちて大怪我をしたので、人々が悔みを言うと、「これが福になるかもしれぬ」と笑っている。しばらくすると戦争が始って若者はみな兵隊にとられて戦死したが、翁と息子は兵役をまぬがれ親子ともども命をを全うしたという。 こんな翁の話を聞くと、すぐに善いとか悪いとかいって一喜一憂している自分が省みられます。「晴れた日は晴を愛し 雨の日は雨を愛す 楽しみあるところに楽しみ 楽しみなきところに楽しむ」とは吉川英治氏の言葉。お互い一寸先は闇の世を生きていますが、氏の言葉のように自分を中心とする考えを去って雨奇晴好 日々好日の一年でありたいものです。皆さまのご多幸を念じ上げます。 |
先日、夜おそく電話がしきりに鳴る。受話器をとると一杯飲んでいるのではないかと思える口調で「和尚さん、私は子供のころ、お寺によく遊びにいっていた○○です」と言う。私はびっくりした。彼は若い頃、故郷を出奔して四十年、親にも兄弟にも音信不通で、皆から死んだものと思われていたからです。「どうして急に電話してきたの」と聞くと、「最近、親父の夢をよくみるのです。親父は生きているのでしょうか」。そこで私が、「おふくろさんは生きているが、親父さんは半年前に死んだよ。墓まいりに帰っておいで」と言うと、「そうしたいけど敷居が高くて帰れない」と言う。そこで私が「それは他人に言う言葉で、親の前に敷居なんかないよ。心配せんで帰っておいで」と言うと、受話器の向うですすり泣きの声が始まり、それはやがて号泣に変った。 その泣き声を聞きながら「人はみな佛性をもっている」と宣言された釈尊の言葉を思いだしました。佛性とは具体的には、できたら悪いことを止めたい、できたら善いことをしたい、できたら人を困らせたり泣かせたりしたくないという三つの気持を言う。人間が尊いのは、この三つの気持をどこかに持っているからで、それ以外の何者でもない。人の話では彼の父は亡くなる時、「息子が孫を連れて会いにきた」と言ったそうです。父は精神錯乱の中で息子に出会い、息子をいい息子と思って死んでいったのです。これを人から聞いたとき、それこそ仏さまの賜物ではなかったかと思った。 |
もう師走、「ふりむけばご恩をうけし人ばかり」で、この一年、自分の命はどれだけ多くの力で支えられてきたことだろうか。天地の力、人の力、いくら考えてもはっきりとわかるものではない。それを昔の人は暗くてよくわからないと行って、「冥加につきる」という感謝の言葉で表していた。 衆議院議員・西川京子さんの後援会の会合であった話。話題がたまたま今、問題にされている慰安婦に及んだ時、一人の老婦人の体験談が人々の心を打った。 「私が二十才のときのこと。髪の毛を切って顔中に墨を塗り、貨車に乗って満州を脱出して朝鮮に入った。しかしそこでソ連軍に拘束され、『女を出せ』ということになった。若い娘たちが、もはやこれまでと覚悟を決めた瞬間、貨車の中の一群の女性が『私たちはどうせ穢れた体。私たちが残るからあなた方はどうか無事に日本に帰って、私たちの分まで幸せになって下さい』といい残して下車していきました」。 その時の彼女たちの姿を想像すると涙が出る。当時の話として中国雲南省ラモウなどでは、朝鮮人慰安婦は連合軍に投降させ、自分たちは弾薬運びをして日本の将兵を助けた日本人慰安婦のいたことなどが報告されている。 慰安婦の中にも、こんな誇り高い人たちがいて、我々もどこかで彼女たちのおかげを頂いている。だから性奴隷などといって彼女たちを卑しめたくない。将兵たちの戦友だった。「ごくろうさま」とせめてその労をねぎらってあげたい。 |
秋こぬと目にはさやかに見えねども風の音にぞおどろかされぬ さしもの猛暑も薄らいで秋の気配がしのびよってきます。日除けのために窓辺に植えられた蔓草は、夏の間は毎日水をかけられて勢いがよかったのですが、最近はすっかり色を失って病葉が目立つようになりました。季節の変りめは諸行無常という仏の教をはっきり思い出させてくれるので有難い。詩人の三好達治氏は、「知性と感情の調和した叙情詩を完成した」と評価されていますが、作品に「かよわい花」という無常観をうたったものがあります。 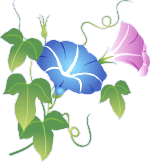 かよわい花です かよわい花ですもろげな花です はかない花の命です 朝咲く花の朝がおは 夕方しぼんでしまいます 夕方に咲く夕がおは 朝にはしぼんでしまいます みんな短い命です けれども時間を守ります そしてさっさと帰ります どこかへ帰ってしまいます ここで言う「時間」とは、点の「時刻」ではなく、長さで「寿命」という意味でしょう。花はみな寿命は短いが、決められた時間を「守ります」、そして最後は「さっさと帰ります/どこかへ帰ってしまいます」・・・・なんと象徴的な言葉ではないでしょうか。念仏の妙好人、荒巻くめさんは、「たましいの行先ここと思いおき浮世のことは柳なりけり」と詠んでいますが、秋はたましいの行先を考え、「今」を生きる問題をいろいろと考えさせられるものがあるような気がします。 |
釈尊のみ弟子にフルナという人がいた。あるとき彼は、ずるくて粗野のうわさが高いシュロナ国へ伝導に行きたいと思い、師に許可を求めた。 すると師は「彼の国の人は狡智にたけていると聞いているが、悪口を言われたらどうするか」と問われた。すると彼は、「まだ打たれないからましだと思います」と答えた。すると師は、「打たれたらどうするか」。彼は「斬られないからましだと思います」と答えた。すると師は、「斬られたらどうするか」と問われた。彼は「まだ殺されないからましだと思います」。すると師は更に、「殺されたらどうするか」と問われた。すると彼は、「その時は見にくい身体の束縛から解放されたと思います」と答えた。すると師は、「よいかなフルナよ、汝はよく道を修め、忍辱を学んだ。シュロナ国へ行って法を弘めよ」と許可を与えた。そしてフルナは伝導に旅立って、三ヶ月で五万の人を教化したと仏伝にある。 9月はお彼岸の月。迷いの此岸から悟りの彼岸へ渡るのに六つの橋があるが、その一つが忍辱である。これは我慢するということだが、単なる我慢ではなく、親が子のために喜んで我慢するように、喜んで我慢するということです。 中国の公船が毎日のように尖閣の領海に侵入している。海上保安庁の方々には心の安まる間もないだろう。このように毎日となると、とてもヤセ我慢では続かない。使命感と国を護るという喜びがなければ続かない。我々が寝ている間も孜々として忍辱行を行じて下さっている保安庁の方々に感謝したい。 |
よく降る雨を見ていたら、京都・南禅寺の門前に住んでいたという泣き婆さんのことを思いだしました。老婆は降っても照っても泣いていました。老婆には二人の娘がいて一人は傘屋に、一人は下駄屋に嫁いでいたが、雨が降ると下駄屋の娘が困る、日照りが続くと傘屋の娘が困るだろうと泣くのです。これをみたある人が、「お前さんは心の持ち方が悪い。雨が降ったら傘屋の娘が喜ぶ、日が照ったら下駄屋の娘が喜ぶと考え方を変えてみたら。物事を悪い方ばかりにとってはいかんよ」と言ってきかすと老婆も納得して、それから降っても照っても日々是好日の人になったという。考えさせられる話です。 でも、それだけでは納得できないものが世の中に多すぎます。会社は潰れた、働き口はない、病気をした、女房は家出した、娘は出戻ってきたというような現実が多々あるのですが、これではとても日々是好日とは頂けません。 こうなって思い出されるのが良寛さんの言葉です。「災難の時は災難にあうがよろしく候、病む時は病むがよろしく候。死ぬる時は死ぬるがよろしく候」。 良寛さんは、受けなければならぬものは素直にハイと頂いていこうと言っているわけです。その境地こそ日々是好日。 南無阿弥陀仏は梵語で、訳せば「アミダさまに全てをおまかせします」となる。 この秋は雨か嵐かしらねども 日々のつとめに田草とるなり おまかせの中に人事が尽せる日々好日の日暮しでありたいものです。 |
足の膝の軟骨がすり減って歩くたびに激痛を覚えていた婦人が、人工関節の手術をうけてから歩くのが嘘のように軽くなった。そのことで彼女が私に「最初は痛い、いたいと人に訴えていたが、言うたびに痛さがつのることに気づいてから言わないようにしていた」と話してくれた。激痛の中で彼女は深い真理を体得して、それを実践していたわけである。 人は自分で言う言葉の力を受ける。ウメボシと言っていると、唾がにじんでくる。暑い時に「暑い、あつい」と言っていると益々暑苦しくなる。「コン畜生」と繰り返していると、心がしだいに荒んでくる。それが言葉の力だろう。 裏千家の千宗室宗匠と俳優の西村晃氏の誌上対談を思いだす。二人は特攻隊員として死ぬことになっていた。宗匠の場合は爆弾を抱えて飛びたった飛行機が途中で故障して引き返したので助かった。その宗匠の話だが、出撃前夜の隊員の宿舎は、黙然と壁に向う者、遺書を書く者等で重く沈んでいた。宗匠はその空気に耐えきれなくなって滑走路に走り出て、京都の空に向って思いきり大きな声で、 「お母ちゃん」と叫んでみた。すると何故か、心のつかえがすっととれて、これで明日は死んでいけるという気になったと語っておられた。「お母さん」と呼ぶことで母の力をもらったのだと思います。 法然上人はお念仏を称えるときは、声にだしてナムアミダブツと称えなさいとすすめておられる。そうすると仏さまのお力をいただくことができるからです。 |
嫌な時代がきました。憲法の前文には「日本国民は平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」とあるが、北朝鮮は日本にテポドンを向け、中国は尖閣を狙う時代がくると、何と日本の憲法は現実離れしているのかと思わずにはおれません。改憲の声が出る中で、思い出されるのが法然上人の伝記の一節です。 ある日、一人の武士が上人のところに来て訴えます。「上司の命令で私はこれから戦争に行かねばなりません。武士の身分も捨てず、人を殺しても仏から見捨てられない道があったら教えて下さい」。それに対する上人の答はこうでした。 「アミダさまのご心配は罪人のためですから、罪人は罪人ながら念仏すればよいのです。あなたがたとえ戦死しても、念仏して終らば、仏のお救いをいただくことを、ゆめゆめ疑ってはいけません」。 武士は涙を流して「これで死んでいけます」と勇んで出陣したと伝記にある。 平和を叫ぶ人から、上人が非難されるのは、この点です。上人はなぜ徹底して反戦を貫かなかったのか、「戦争に行ってはいけない」と言はなかったのかということです。その点で私はこう思います。上人は人間の悲しい業をよくご存知だったからではないかと思うのです。戦争を止めることができないのが人間の愚かな業なら、せめて安心して死なせてやりたいという慈悲の心が、この武士に対する、このような餞別の言葉になったのではないかと思います。 |
3月11日、東日本大震災で逝った人の三回忌がめぐってくる。南三陸町に慰霊の観音像建立を発願している人の話によると、被災地では、いまだに行方不明になった人が道を歩いていたとか、玄関の戸を叩いたとかの話が絶えないらしい。幽霊話の時代ではないというかもしれないが、そのように思っている人には事実そのもので、そこが大事なところである。 明治35年、日露戦争に備えて、青森連隊の二百余名が八甲田山で雪中行軍をした。衣服、食料、体力疲労等を研究するためである。その結果、大方は凍死してしまい、残存者は十余名という大惨事に終った。その直後から連隊の衛門に向って行軍の靴音が近づいてくるので衛兵は震えあがった。うわさを聞いた連隊長が一夜衛舎に詰めていると、衛兵が「今、靴音が近づいてきます」という。たしかに闇の中から多数の靴音が近づく気配だ。すると連隊長は抜刀して闇に向って、「お前たちの死は犬死ではない。寒中の装備、食糧は改善され、来るべき有事の際には役立つ。安心してくれ。『廻れ右、前へ進め』」と大声で号令すると靴音は遠ざかっていき、以来、音は絶えて聞かれなくなったという。 予想される南海大地震に備えて、今、沿岸各地で防災計画がすすめられている。大分では佐伯市米水津がそうだし、高知の黒潮町では35メートル級の津波から犠牲者ゼロをめざす大計画がたてられ、それが着々実行されている。あなたたちの死は犬死ではない。それを知ってもらい、死者を追悼して三回忌の供養としたい。 |
2月15日はインドでお釈迦さまが亡くなられた日。その様子は涅槃経に述べられているが、老齢で死期の近きことを悟られたお釈迦さまは、弟子一人を連れて故郷に向っておられた。途中で鍛冶屋のチュンダの家で説法され、昼食の供養を受けられたが、料理の中に毒茸が入っていたらしく、下痢をして衰弱された。皆がチュンダの不注意をせめるのを見て、お釈迦さまは彼を呼んで言れた。 「気にすることはない。私には二人の恩人がある。一人は私が若いころ、激しい苦行のために死にかけていた時、私を助けおこして牛乳を飲ませてくれた村娘のスジャータである。もう一人はお前だ。私が死ぬのは生れたから死ぬので、お前のせいではない。お前の料理は、私に死のチャンスを与えてくれた。おかげで八十年の生涯を閉じることができる。ありがとう」 「深く諦観し恨みなき心に立ち返るとき、安らぎが訪れる」とは釈尊の金言。 法然上人の父は、上人が九才の子供の時、闇討ちにあって目の前で斬殺された。その時の遺言は、「お前は決して仇討ちをしてはいけない。そうすれば向うにも子供がいるから、争いは永遠に続く」というものだった。 北条時宗は蒙古襲来戦の後、鎌倉円覚寺に敵味方供養の碑を建て、戦死した敵兵の菩提を弔った。豊臣秀吉も朝鮮出兵では、同じような碑を建て敵を弔った。 東洋人にはお釈迦さまと同じような血がどこかに流れているから、そのようなことができたのだろう。怨親平等の東洋の思想は人類の宝物である。 |
諸橋轍次「十二支物語」(大修館書店)で「巳」の項を見ると、人に嫌れる蛇にも意外にエピソードが多いのに気づく。これはその一つ。 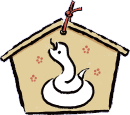 古代中国の聖人・荘子は斉物論で愚かな人を蛇にたとえて、「蛇のうろこか、蝉のつばさか」と笑っています。蛇は自分の力で動くのだと思い、うろこも自分の力で動くのだと思っている。蝉とそのつばさも同様に、自分の力で飛ぶのだと思っている。 古代中国の聖人・荘子は斉物論で愚かな人を蛇にたとえて、「蛇のうろこか、蝉のつばさか」と笑っています。蛇は自分の力で動くのだと思い、うろこも自分の力で動くのだと思っている。蝉とそのつばさも同様に、自分の力で飛ぶのだと思っている。しかし、これはどちらも間違いで、蛇や蝉は、うろこやつばさが陰の恩人となって、はじめて動き、飛ぶことができている。その道理を知らない人を荘子は愚人といって笑ったのです。 思えば人はみな、陰の恩人に支えられて生きている。映画監督の山田洋次さんは、学生のころ下宿近くのたばこ屋の親父さんのことを、エッセーで紹介している。その親父さんは、山田さんが「ピース」と言うと、「学生のくせにぜいたくだ」といって「新生」しか売ってくれなかった。山田さんは親父さんを通して、他人の子でも自分と無関係な者はいないという大事な感覚を身につけたはずです。いわば親父さんは山田さんの青春を脇で支えた陰の恩人で、こんな人たちがうろこの役を果たしてくれたから、山田さんが一人前になれたのです。 この一年、うろこのおかげのわかる巳年としたい。 |