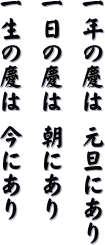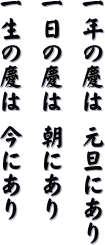|
|
 |
明治の政治家として日朝修好条約を結び、外相、農商務相、内相、蔵相などを歴任し、晩年は元老のひとりとして政界に臨んだ長州藩士、井上馨は「母の力」によって誕生したと言っても誤りはない。
名を聞多と名乗っていたころ、暴漢に襲われて瀕死の重傷を負う。もはやこれまでと、聞多は兄に介錯を頼む。涙ながらにうなずいた兄は決然として刀を抜く。
この続きは『小学館読本・巻十』で紹介しよう。
|
「待っておくれ」それは、しぼるような母の声である。母の手は、堅く五郎三郎の袖にすがっていた。
「待っておくれ、お医者もここにいられる。たとえ治療はかなわないにしても、できるだけの手を尽くさないでは、この母の心がすみません」
「母上、こうなっては是非もございませぬ。聞多の体には、もう一滴の血は残ってはいませぬぞ。手当をしても、ただ苦しめるばかり。さあ、お放しください」
兄は刀を振りあげた。その時早く、母親は血だらけの聞多の体をひしと抱きしめた。
「さあ、切るならこの母もろ共に切っておくれ」
この子をどこまでも助けようとする母の一念に、はりつめる兄の心もゆるんでしまった。
聞多の友人、所郁太郎がその場へかけつけた。彼は蘭方医であった。
彼は、刀の下緒をたすきに掛け、かいがいしく身支度してから、焼酎で血だらけの傷を洗い、有合せの小さい畳針で傷口を縫い始めた。聞多は、痛みも感じないかのように、こんこんと眠っている。
(中略)
それから幾十日、母の必死の看護と医者の手当てによって、不思議にも一命を取止めた聞多が、当時の母の慈愛の態度を聞くや、病の床にさめざめと泣いた。
「聞多、三十才の壮年に及んで、何一つ孝行も尽くさないのに、今母上の力によって、万死に一生を得ようとは」 |
この母の力なくして井上馨の活躍はない。「まことにありがたく尊いのは、この母の力」とこの文章は結ばれている。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
上は平成24年12月5日付、産経新聞の「教育」欄の「消えた偉人物語」をそのまま転載したものです。
偉人と呼ばれた人たちが日本を導いてくれたことを、今の子供はあまり知りません。同様に、親の深い愛の姿もあまり知りません。教えられてないからです。なぜ教えられないのでしょうか。横並びの教育を遍重する結果がそんな傾向を生んだのです。横糸だけでも、縦糸だけでも布は織れません。横糸だけで織ろうとして、あちこちに破綻をきたしているのが今の日本の姿です。バランスのある日本の心をとりもどしたおものです。 |
| (閑院) |
|