|
|
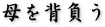 |
| 石川啄木は明治19年に岩手県で生れた。生れつきの病弱で父母を心配させたという。17才の時、彼の短歌が文芸雑誌に掲載され、天才歌人と騒がれた。だが、貧乏で借金が重なって、21才の時に一家が離散する。啄木は母を知人に預け、妻子を実家に帰して、生活を立て直すため北海道の新聞社に就職した。しかし、東京で新しい文学運動がおこると、じっとしておれなくて、1年後に仕事を辞め、単身、東京へ行った。だが小説は売れず借金は増え、その上、不眠に悩まされて自殺を考えるまでになった。そんなある夜、啄木に吹き上げるように歌が次々と浮んできた。その一晩に百四十首の歌が生れている。その中の四十余首が父母を詠んだ歌で、泣きながら歌をつくったと、日記に記している。この時の作品は彼の代表的な歌集『一握の砂』に掲載されているが、その中に、 |
|
たはむれに母を背負いて
そのあまり軽きに泣きて
三歩あゆまず |
|
という歌がある。やがて啄木は結核性腹膜炎で入院。重症にもかかわらず入院費が払えず退院。病は肺結核に移行し、26才の若さで天才は逝った。
「たわむれに母を背負いてそのあまり軽きに泣きて三歩あゆまず」
これはよくお寺の法話の中で引用される歌です。私も時々、引用させてもらっていますが、あるお寺の法座で、
「啄木の母は吾子がどうしているかと心配なあまり軽くなったのである。だからこの軽さは単なる軽さではなく、親の慈愛の重さである」と言って法話を終えて控室に戻っていると、今まで本堂で話を聞いて下さっていた一人の男性が部屋に来て、
「母を背負うの歌のことですが、啄木という男は母を背負ってその軽さに泣くような、そんなやさしい男ではない、ということを啄木の実の妹が私の読んだ本の中で証言していますよ」
私は絶句しました。どう答えてよいか言葉を失ってしまったのです。たしかに啄木の妹がいうのですから、それは真実かもしれません。その時、ふと思い出されたのが芥川龍之介の小説「蜘蛛の糸」です。その小説の主人公・カンダタは極悪非道で生れてからこのかた一度も善いことをしたことがないという男です。その彼がある日、森の中を歩いていると道を一匹の蜘蛛が横切ろうとしている。いつもならエイッと踏みつぶしていくのだが、その日はどんな風の吹きまわしか、「こいつにも親や子があるかもしれぬ」と思って跨いでいった。それをじっと見ていたお釈迦さまは、このたった一つの善根を手がかりにカンダタを極楽へ連れていくのです。彼のことを思いだしたので、私はこの人に申しました。
「カンダタのように平素は想像もできないことを“はずみ”でするのが人間です。啄木も平素は冷たい男であったとしても、ふとしたはずみで、母を背負って泣いたこともあったのではないでしょうか。いろんな局面をもっているのが人間ですからね」 |
| (閑院) |