|
|
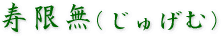 |
待望の男の子が生れて大喜びの親父、立派な名前をつけてやりたいと思うが、なかなか浮かばないので、寺の和尚に頼みに行った。
「なにかこうー死なねえ保険付きろいうようなすてきな名前を頼みます」
「それはむずかしいな。生あるものは必ず死す。なれど長生きを祈るというのならある。鶴吉というのはどうかね。鶴は千年の寿を保つという」
「それはいけねえ。千年というと千年たちゃ死んでしまう。ありませんかね、もっと長えのは」
「それなら亀は万年というから、亀の字をとったらどうか」
「いけねえ、いけねえ。亀の字なんど、縁日でぶらさげられていて、頭を突かれたら首をちぢめる。人に頭を押さえられてちゃあ出世ができねえ」
「それなら松はどうか。これはめでたい」
「松はいけねえ。植え替えると、じきに枯れちゃう。土地が変わるたびに枯れてしもうては引っ越しもできねえ」
「竹は丈夫なものだが、どうかな」
「筍は出るとみな、へし折られてしまう」
「なら、梅はどうじゃ」
「いけねえ、いけねえ。花が咲けば枝を折られる。実がなりゃあもがれる。おまけに樽の中に押し込まれてしまう。これじゃ世の中へ出ることができねえ」
「そういちいち理屈をつけられてはどうもならん。では経文の文字ではどうじゃ」
「お経でもなんでも長寿をすればいいんだ」
「それならいくらでもある。寿限無というのはどうじゃ」
「なんです、それ?」
「『寿、限り無し』といってな、つまり、死ぬ時がないということじゃ」
「それはありがてえ。もうほかにありますめえか」
「まだまだ、いくらもあるよ。五劫の摺り切り・・・」
「なんだね、そのゴボウのスリキレってのは」
「ゴボウじゃない、五劫だ。一劫というのは百年に一度天女が天降って下界の大岩を衣でなでる。それで岩が摺り切れてしまうのを一劫というんだ。五劫というから、何億年か、数えつくせない。」
「しめしめ、それがいい、まだありますが」
和尚と男の会話はまだまだ続いて、ようやく出尽くしたところで男は言った。
「じゃあ、すみませんがね、その初めの寿限無から最後の長助まで、書いてみておくんなさい」
「よしよし、平仮名でわかるように書いてしんぜよう。この中から、いいのをお取んなさい」
「へい、ありがとうございます。最初が寿限無ですね。寿限無寿限無、五劫の摺り切り、海砂利水魚の水行末、雲来末風来末、ヤブラコウジのプラコウジ、パイポパイポ、パイポのシューリンガン、シューリンガンのグーリンダイ、グーリンダイのポンポコピーのポンポコナの長久命の長助か。なるほど。どれをつけても、具合が悪かった時に、あれにすりゃよかった・・・というような愚痴が出るといかねえから、めんどくせえ・・・みんなつけちゃおう」
ご存知、落語の「寿限無」だが、こんな笑い話の中にも、わが子よかれと祈る親心が光っている。 |
| (閑院) |
|
