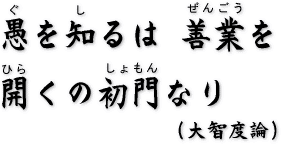|
|
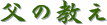 |
|
私にとって幸運だったのは、ことあるごとに武士道精神をたたきこんでくれた父がいたことでした。父からいつも「弱いものいじめの現場をみたら、自分の身を挺してでも、弱い者を助けろ」と言われていました。
父は「弱いものがいじめられるのを見て見ぬふりをするのは卑怯だ」と言うのです。私にとって「卑怯だ」と言われることは「お前は生きている価値がない」というのと同じです。だから、弱いものいじめを見つけたら、当然身を躍らせて助けに行きました。
私は体格がよく力も強かったので、必ずいじめている者たちを蹴散らしました。それを報告するたびに父は喜んでくれました。あれほど喜んでくれたことは、他にはほとんど思いつきません。母は渋い顔で、「正義の味方もほどほどよ。暴力少年のレッテルを貼られ、内申書にでも書かれたら、行きたい中学にも行けませんよ」なって言ってましたが。
 父は「弱いものを救う時は力を用いても良い」とはっきり言いました。ただし五ツの禁じ手がある。一つ、大きい者が小さい者をブン殴ってはいかん。二つ、大勢で一人をやっつけてはいかん。三つ、男が女をぶん殴ってはいかん。四つ、武器を手にしてはいかん。五つ、相手が泣いたり謝ったりしたら、すぐやめなくてはいかん。「この五つは絶対に守れ」と言われました。 父は「弱いものを救う時は力を用いても良い」とはっきり言いました。ただし五ツの禁じ手がある。一つ、大きい者が小さい者をブン殴ってはいかん。二つ、大勢で一人をやっつけてはいかん。三つ、男が女をぶん殴ってはいかん。四つ、武器を手にしてはいかん。五つ、相手が泣いたり謝ったりしたら、すぐやめなくてはいかん。「この五つは絶対に守れ」と言われました。
しかも、父の教えが非情に良かったと思うのは、「それには何の理由もない」と認めていたことです。「卑怯だから」でおしまいです。
で、私はその教えをひたすら守りました。例えば「男が女をぶん殴ってはいけない」と言ったって、簡単には納得しにくい。現実にはぶん殴りたくなるような女は世界中に、私の女房を筆頭に山ほどいる。どんなことがあってもいけない。そういうことをきちんと形として教えないといけないということです。
  |
上は、お茶の水女子大理学部数学科教授・藤原正彦著「国家の品格」(新潮社)の一節。同書は現在ベストセラーを続けているものだが、著者は私の精神の基盤は、幼い頃から父にたたきこまれた武士道精神への帰依であると言っている。その武士道精神について新渡戸稲造の名著「武士道」には、それは「惻陰の情」を基盤とすると述べられている。要するに、敗れた者、劣った者を思いやる心がそれである。武士道精神というと、今日では時代おくれのもののように受けとられがちだが、しかし、それは仏教の慈悲の精神にも深く通ずる精神であることがわかる。
尚、藤原正彦氏は作家新田次郎、藤原ていの子息で、「天才の栄光と挫折」等々、著書多数あり。 |
| (閑院) |
|