|
|
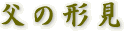 |
|
昭和23年2月、島根県の山奥育ちの少年は、父を失い、母と妹をみなければならなくなったので、職を求めて東京に行った。駅に降りて少年は愕然となった。母が家の全財産を持たせてくれた財布をすられていたのに気づいたからである。2、3日はたくあんだけで食いつないできたが、それだけではどうにもならない。やむなく母が持たせてくれた形見の着物を持って質屋に行った。はじめての体験でもじもじしている少年に店の親父が「どうした」と声をかけてきた。「これをお願いします」と少年が着物を出すと、「これはどこから持ってきた?」と親父。上京の折、母が持たせてくれたことを話すと、「親の形見なんか持ってくる奴がいるかッ」と。ポカリと親父のゲンコツが飛んできた。それでも15円を貸してくれた。
「これを持ってこれからどうするんだ」、「はい、食堂へまず行きます」
すると親父は奥へ向って、「おーい。この子に飯を食わせてやれ」
 すると奥さんは「うちは食堂ではありません」と小言をいいながらも奥に通されていった。みそ汁とたくあんだけの食事だったが、この時のおいしさといったら、なかった。礼を言って帰ろうとすると、親父からまた一言、「いいか、おそくなってもいい。必ずこれを受け取りに来いよ」少年は亡き父と全く変らぬ温かさと厳しさに触れて、固く約束して店を出た。それから半年、町工場で働きながら質受けの金をためた少年は、親父さんに喜んでもらおうと寿司折を土産に店を訪ねた。しかし出てきたのは親父の息子さんだった。「親父は二ヶ月前に亡くなったよ」 すると奥さんは「うちは食堂ではありません」と小言をいいながらも奥に通されていった。みそ汁とたくあんだけの食事だったが、この時のおいしさといったら、なかった。礼を言って帰ろうとすると、親父からまた一言、「いいか、おそくなってもいい。必ずこれを受け取りに来いよ」少年は亡き父と全く変らぬ温かさと厳しさに触れて、固く約束して店を出た。それから半年、町工場で働きながら質受けの金をためた少年は、親父さんに喜んでもらおうと寿司折を土産に店を訪ねた。しかし出てきたのは親父の息子さんだった。「親父は二ヶ月前に亡くなったよ」
少年は絶句した。せめて仏壇におまいりさせてほしいと頼んで、仏前に寿司を供えて手を合せていると、涙がじわりとにじんできた。それから質の元金と利子を出すと、息子が蔵から着物を出してきた。包装をほどくと父の形見の着物が出てきて、その上に1枚の紙片が添えられていた。それにはただ一言「利子はとるな」と書かれていた。
少年はまた絶句して涙が堰を切ったようにあふれてきた。 |
|
上は「心に残るとっておきの話」(潮文社)に、涙を流した当人が寄せた一文の要約である。本人は今、川崎市で一級建築士として一家を成しているが、文末に「あれから川崎市での45年間の生活を親父さんが陰から、どんなに励ましてくれたことか。自分も片隅の人でいい、親父さんのような人間として生きたいと思ってきた」と記している。
それにしても、見ず知らずの少年を「親の形見を質入れするような奴がいるか」と叱るような質屋の主人のようなタイプの人間が社会からめっきり減った。たとえ見知らぬ家の子でも、どこかに子供を見る目に温かみがあったのが、かつての日本人だったように思う。だから子供たちは日の暮れるまで安心して戸外で遊べたのである。
「個」のみが強調され、「公」の精神が薄れたことがそのような温かみを奪ったのではないか。
「うつくしき清きこころのくにたみの 満ちいし日本よいずこへゆきし」(西川京子)
|
| (閑院) |
|
