|
|
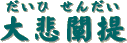 |
|
私は小学校三年の時に小児結核で入院した。病名が決った日から、父は煙草を断った。長期入院、山と海への転地。
「華族様の娘ではあるまいし」
親戚からかげ口を利かれる程だった。家を買うための貯金を私の治療費に使ってしまったという徹底ぶりだった。病院へ通院していた頃、母はよく私を病院の近くの鰻屋へ連れて行った。隅のテーブルに向かい合って坐ると、母は鰻丼を一人前注文する。鰻は母も好物だが、
「母さんは今日はおなかの具合がよくないから」
「油ものは欲しくないから」
口実はその日によっていろいろだったが、つまりはそれだけゆとりがなかったということだろう。保険会社の安サラリーマンのくせに外面のいい父。親戚には気前のいいしゅうとめ、そして四人の育ち盛りの子供たちである。この鰻丼だって、縫物のよそ仕事をして貯めた母のへそくりに決まってる。私は病院を出て母の足が鰻屋に向うと、気が重くなった。おばあちゃんや弟妹達に内緒で一人だけ食べるというのも嬉しいのだが、うしろめたい。どんなに好きなものでも気が晴れなければおいしくないことを教えられたのは、この鰻屋だったような気もするし、反対に、多少気持はふさいでいても、おいしいものはやっぱりおいしいと思ったような気もする。どちらにしても、食べ物の味と、人生の味と、ふたつの味わいがあるということを初めて知ったということだろうか。 |
上の「私」というのは作家の向田邦子さんのことで、彼女の短編「ごはん」の中で語られている母の思い出である。この中で、貧しい母が病気の娘に食べさせたくて、自分はおなかの具合が悪いからと娘一人に鰻丼を食べさせる母のことが述べられている。戦前戦後の食料難時代を知る者なら、自分のことと思い合せて、胸にジーンとこみあげるものがあるはずである。向田さんは同じ「ごはん」の中で
|
「おいしいな、幸せだなと思って食べたごはんも何回かあったような気がするが、その時は心にしみても、ふわりと溶けてしまって不思議にあとに残らない。思い出すのは、しょっぱい涙の味がしたごはんの味だけである」 |
と述べているが、まさに同感で、自分もまた、子供のためにささげ尽くして、むしろ、それを生甲斐としていたような親の姿だけが思い出される。
仏語では親のことを「大悲闡提」と言う。闡提とは地獄の住人よりも救われ難い人のことで、地獄の住人は一定期間が過ぎると浄土に生まれ代ることができるが、闡提は未来永久に浮かばれない。その上に大悲という慈悲の名が冠せられているのは意味深い。親とは子を思うが故に、未来永久に救われない人のことを言うのである。 |
| (住職) |
|
