|
|
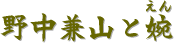 |
土佐藩奉行・野中兼山は傑出した政治家であった。河川をつくり、新田を開き、港を整備して土佐二十四万石を実収三十万石にまで高めた。政務の奔走するあまり、睡眠時間は常に4時間であったという。だが、「出る釘は打たれる」が世のならい。政敵に足をすくわれ藩主から蟄居を命じられるところとなる。気落ちした兼山は、それから3ヶ月後、急死した。冷酷な藩の仕打ち家族の上にまで及んだ。家族は罪人扱いとなり、家はとりつぶし、領地は没収、その上、子女8人は「宿毛へ配流申し付ける」という沙汰が下った。政敵たちは、それほど兼山の功績を打ち消すことに力を注いだのである。
 8人の子女のうち三女が婉(えん)という娘だった。彼女はこの時4才、土佐出身の作家・大原富枝は「婉という女」で、婉は「学問、人徳、容貌ともすぐれた稀代の才媛」だったと述べている。幽閉生活は一般社会から完全に隔離され、かやぶきの獄舎は周囲を竹矢来で囲まれ、番卒が警備し兄妹らは門外に一歩も出ることも許されないという厳しいものであった。小説では婉の独白というかたちで 8人の子女のうち三女が婉(えん)という娘だった。彼女はこの時4才、土佐出身の作家・大原富枝は「婉という女」で、婉は「学問、人徳、容貌ともすぐれた稀代の才媛」だったと述べている。幽閉生活は一般社会から完全に隔離され、かやぶきの獄舎は周囲を竹矢来で囲まれ、番卒が警備し兄妹らは門外に一歩も出ることも許されないという厳しいものであった。小説では婉の独白というかたちで
「私たち兄妹は誰も『生きる』ことをしなかった。ただ、『置かされて』いただけだ。」
と述べている。
そのような境遇の中で、婉が43才になって一家が赦免されるまで40年間を獄舎で過すのだが、その間、兄妹たちは父兼山に対して、どのような思いをいだいて過してきたのだろうか。ある時、泣いている婉に兄が言う。
「そんな弱虫では父上のような立派な人間にはなれんぞ」
またある時、婉が兄に言う。
「父上という方がどんなお方であったのかを知りたいと思います。私たちにまで及ぶ、このような憎しみは、いったいどこから沸きだしてくるのか知りたいのです」
それに対して兄は、
「私は父上ほどの人の子に生れて、生涯を獄舎に果てることを無念とは思わぬ」
婉は、時々獄舎に通ってくる医者を通して密かに医術の勉強をつづけており、赦免されてから貧しい者には無料で診察する評判の女医となった。しかし、どんなに以来されても武士の脈だけは決してとろうとしなかった。
親子の絆というにはあまりにも過酷な運命の父と娘。その娘が父を誇りに思いつづけていたことが小説の中ではこんなエピソードとして述べられている。
ある日、籠で城下まで出かけた婉は馬に乗った武士に出会った。あわてて道のわきに籠を寄せようとする籠屋に、婉はそれを制して言った。
「こなたは前の執政野中兼山の娘、その斟酌(心配)は無用ぞ」
籠はそのまま武士をすれ違ったという。
父の罪なき罪を背負って、父を慕いつづけた娘。希有な親子の愛である。 |
| (住職) |
|
